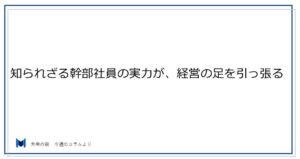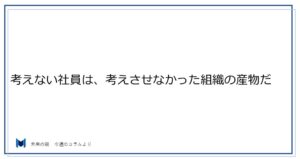第118号:社長はなぜ誰にも相談できないのか?その理由と打開策を徹底解説
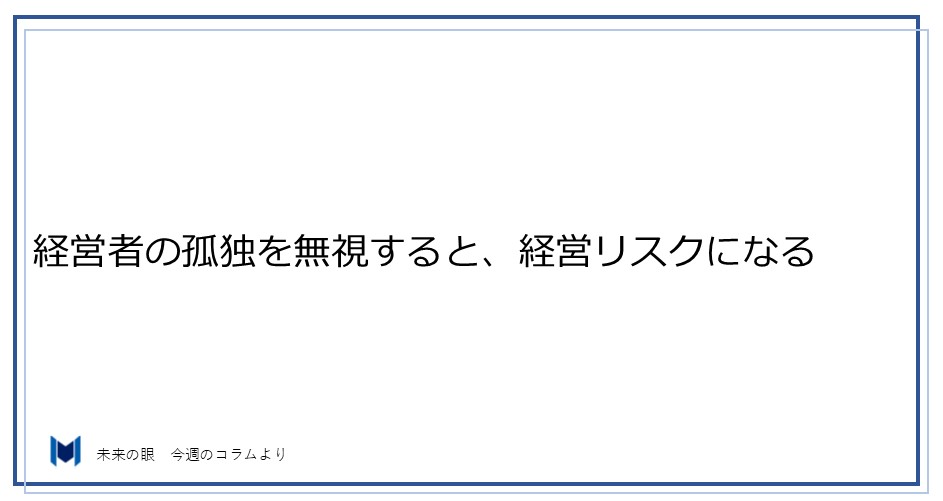
経営者同士が集まる会合などでは、成功事例や最近の投資話、最新のビジネストレンドが飛び交います。誰もが前向きな姿勢を見せ、多少の困難も笑って乗り越えているように見えます。しかし、「実は幹部がまったく育たない」「後継者のことで頭を抱えている」「利益は出ているのに資金繰りが苦しい」、そうした本音を率直に語り合える場は、驚くほど少ないです。
そのため、「自分だけがこんなに悩んでいるのではないか」という孤独感を抱えている社長が、実際には少なくありません。特に中小企業の経営者ほど、その傾向は強くなります。会社の未来を左右する経営判断、従業員の人生を背負う雇用責任、資金繰りや取引先との交渉、そして時には家族の生活まで含めたリスクを一身に背負います。
外から見れば「自由に経営できて羨ましい」「成功していてすごい」と言われることもありますが、経営の現場に立っている当人にしかわからない「重圧」と「孤独」が、常に背中にのしかかっています。
とりわけ問題なのは、「誰にも本音で相談できない」状態に陥ることです。多くの社長が、人材や組織に関する悩みを抱えながら、それを吐き出す場所も、受け止めてくれる存在も持っていません。これは単なる感情的な問題ではなく、経営の持続性や成長性に関わる重要なテーマです。
では、なぜ社長は「相談できる人」を持てないのでしょうか。その背景には、経営者という立場が抱える特有の構造や心理、そして組織の文化が深く関わっています。社長という立場は、組織の最上位にある存在です。「すべての責任は自分にある。従業員に弱音を見せることはできない。」そう思っている経営者は少なくありません。
部下には立場の違いから理解されにくく、幹部には遠慮が働きます。社外の人間に相談するにも、信用問題や情報漏洩のリスクを考えると、踏み込んだ話ができず、結果として「本音で話せる相手がいない」状態が常態化してしまいます。
このような孤立は、社長個人の性格やスキルの問題ではありません。むしろ、組織の構造や経営者に求められる役割そのものが、社長を孤独にしやすい状況を生み出しています。
一方で、「誰にも相談できない」という状態は、思考の偏りや独善的な判断に陥りやすくなります。視野が狭まり、柔軟な発想ができなくなる。その結果、変化の激しい時代に対応できなくなり、事業の方向性を誤る危険性が高まります。
さらに問題なのは、精神的な疲弊です。決して表には出さないものの、孤独な意思決定を繰り返すことで社長自身が消耗していきます。
このような状態から抜け出すためにも、「相談できる人」や「本音や本気度を伝えるべき人」を社内外に確保しておくことが必要です。本音が言える存在がそばにいることで、判断に迷いがあっても第三者的な視点を得られ、冷静かつ戦略的に意思決定できるようになります。
特に社内の「相談できる右腕」を持つには、社長の発言が常に正解とされるような雰囲気があると、自分の意見や考えを言ってもいい、否定されないという安心感を与えることも必要です。加えて、経営に関する対話や意思決定プロセスへの関与といった経験を積ませることで、右腕としての感度が高まります。
また、評価制度の問題も見逃せません。短期成果ばかりを評価する仕組みでは、経営的視点を持つ人材は育ちません。経営に関する対話や意思決定に関わる経験を積ませることが必要ですが、それが設計されていない会社では、いくら時間が経っても「右腕」は生まれないのです。
誰にも相談できないという状況は、もはや特別なことではなく、多くの経営者が抱えている共通課題です。大切なのは、それを放置せず、対話の場を自らつくることです。経営者の孤独は、静かに、しかし確実に事業をむしばみます。だからこそ、「本音を語れる場」「信頼できる対話相手」を確保することが、今の時代における重要な経営課題なのです。
あなたが抱えている悩みや葛藤は、“あなただけのもの”だと思い込んでいませんか?
その想いを言葉にしたとき、経営の質や組織の未来が変わるとしたら、あなたは誰に、何を話しますか?