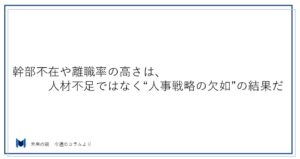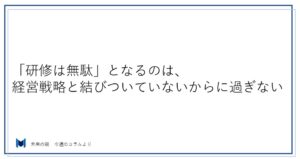第136号:幹部不在が会社を潰す
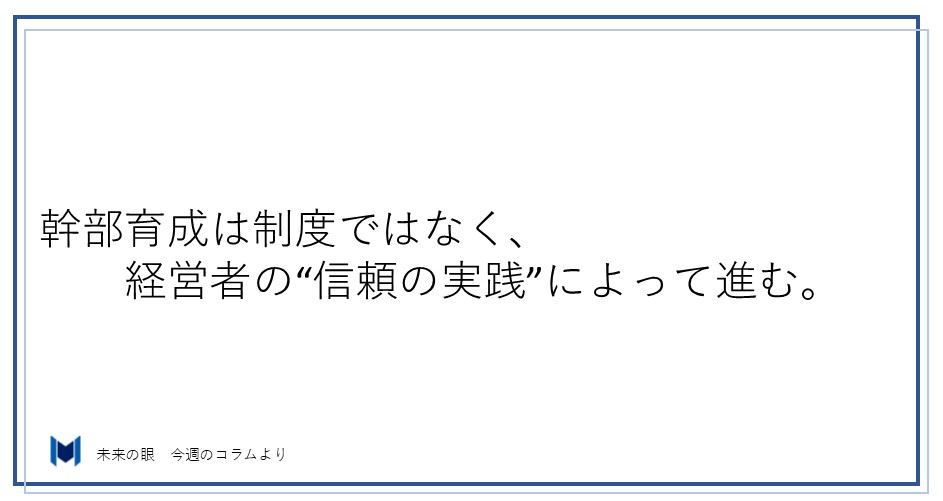
幹部に任せられない社長の本音
「幹部にもっと任せたい。でも、結局は自分で判断してしまう」多くの経営者が口にする本音です。
営業現場でトラブルが起きたとき、幹部に処理を任せるつもりが、気づけば社長自ら顧客先に足を運んでいる。重要な契約を前に、幹部の提案を最後まで聞くことなく「それじゃダメだ」と修正してしまう。幹部に期待していながら、実際には「調整役」にしかなっていない、そんな状況に心当たりはないでしょうか。
これは単に幹部の力量不足ではなく、経営者側の姿勢や仕組みに起因する問題です。
なぜ幹部が育たないのか
1. 経営者の“プレーヤー依存”
多くの経営者は、自らが主導して現場を動かすことで成果を積み上げてきています。そのため、幹部には「社長の補佐役」しか求めなくなり、意思決定の経験を与える機会を奪ってしまいます。結果、幹部は育たず、社長への依存が強まります。
2. 人事制度の断片化
評価、給与、育成、採用がバラバラに存在し、それぞれが戦略に結びついていないケースが目立ちます。そのため、幹部がどのような資質を備えるべきかが不明確になり、人材の成長が場当たり的になってしまうのです。
3. 短期志向の経営
「今期の売上をどう伸ばすか」という短期的な課題ばかりに追われ、幹部育成という中長期的テーマが後回しにされがちです。その結果、数年後に幹部不在という致命的な経営リスクを迎えることになります。
幹部が機能しないと何が起きるか
ある企業では、幹部が意思決定できずに社長へ全てを持ち込み、クレーム処理から採用面接まで社長が対応する羽目になりました。結果、現場社員は「どうせ最後は社長判断」と考えるようになり、幹部を軽視する文化が根付いてしまったのです。
別の企業では、幹部が責任を取らないまま昇進したことで、社員はリーダーに不信感を抱き、優秀な人材ほど辞めていきました。幹部が機能しない組織は、単に“伸びない”だけでなく、崩れていくリスクを孕んでいます。
経営者にしかできない幹部マネジメント──信頼を軸にする
幹部を育てるうえで、経営者が果たすべき最も重要な役割は「信頼を与えること」です。幹部は能力が高いから育つのではなく、責任を与えられ、信頼を寄せられて初めて成長します。
・任せる姿勢を示す
社長が全ての判断を握っていては、幹部はいつまでも「実務の延長線」でしか動けません。たとえ不安があっても、重要な会議や顧客交渉、採用の最終判断を幹部に委ねる。失敗はフォローできる仕組みを整え、成功体験を積ませることが、幹部を「責任を持つリーダー」へと変えていきます。
・幹部を“社長の代弁者”から“経営の共同責任者”へ
幹部を単なる「伝達係」として扱うと、現場は「社長の言葉しか重みがない」と感じてしまいます。逆に、経営の意思決定に幹部を参画させ、結果責任を共有させることで、幹部は「自分も経営の一翼を担っている」という自覚を持ちます。これが幹部の覚悟を磨き、組織に信頼の連鎖を生むのです。
・透明な対話を重ねる
信頼は一度の任命では築けません。経営者自身が考えている未来像や不安を率直に語り、幹部からの意見や疑問を正面から受け止める対話を積み重ねることが不可欠です。このやり取りを通じて幹部は「社長に信頼されている」という実感を持ち、その信頼を部下へと波及させていきます。
幹部マネジメントは信頼関係構築
幹部マネジメントは、単なる人材育成ではありません。幹部に意思決定を委ね、責任を持たせ、信頼を与えることです。
幹部を「社長の補佐」に留めるのか、「次世代の経営パートナー」へと育てるのか。
その選択は、経営者の姿勢によって決まります。
あなたが不在のとき、会社は本当に動ける仕組みになっていますか?