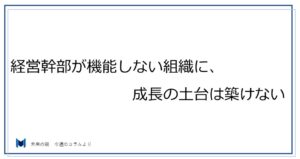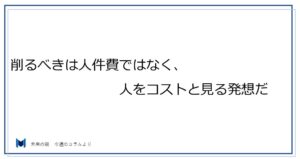第127号:なぜ、あなたの言葉は社員に届かないのか?
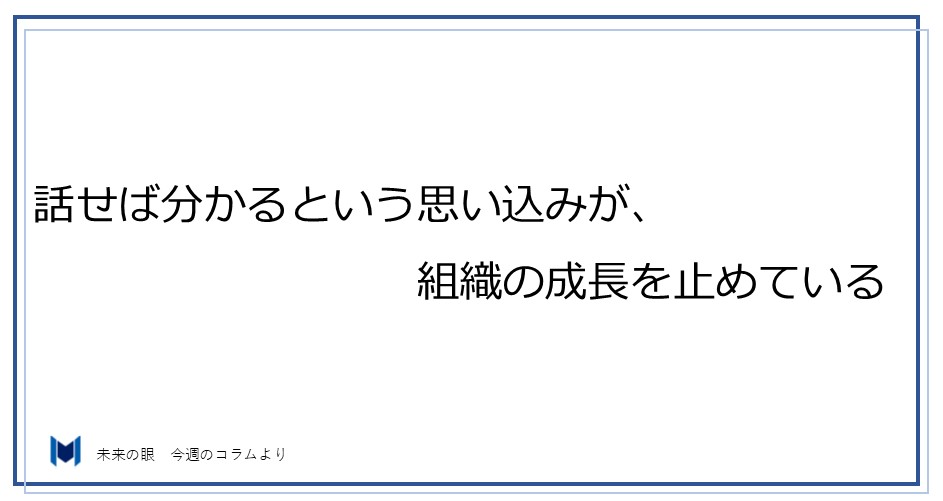
「社員に分かるように、きちんと説明にしているんですよ。それなのに、なぜ、伝わらないんですかね?」、「うちの社員は、言われたことすらできないんですよ…」と、もどかしさを抱えている経営者からよく言われることです。
経営会議や現場ミーティングの場で、何度も「こうしてくれ」「こう考えてほしい」と伝えてきたにも関わらず、
指示とは異なる動きを目にして、フラストレーションを溜めてしまうことはありませんか。「話せば分かる」と信じて疑わない、その信念は、組織作りや人事施策に大きな影響を与えます。
経営者が「話せば分かる」と思ってしまう背景には、相手も自分と同じように物事を理解し、同じ言葉で同じ意味を受け取っているはずだという期待があります。当然のことですが、経営者自身にはこれまでの培ってきた価値観、経験、考え方を持っています。
つまり、経営者が発するその言葉には、経営者としての意図が込められています。ところが社員は、そのような背景や前提知識を持っていないことが多く、同じ言葉でも全く違う意味で受け取ってしまうことがあります。このギャップこそが、現場での「やったつもり」「聞いていない」といったすれ違いを生み、経営者の「言っても伝わらない」という落胆につながるのです。
当たり前のことではありますが、社員は経営者と同じ視点で物事を見ていません。現場の作業や目の前の業務には詳しくても、会社全体の数字やリスク、戦略的な背景までは把握していないのが普通です。つまり、同じ言葉を使っていても、経営者と社員では「まったく違う意味」で受け取っていることがあるのです。
このような「言葉のズレ」が原因で、現場では、
「やりました」
「そういう意味だとは思いませんでした」
「言われていません」
といったすれ違いが起きてしまいます。
そして最終的に、社長は「言っても伝わらない」「もう何を言っても無駄だ」とがっかりすることになるのです。
このような経験をしているにも関わらず、経営者は「話せば分かる」と思ってしまうのは、なぜでしょうか。多くの場合、「話せば伝わるはず」と考えているからです。話せば理解し合えると思い込むのは、これまでの成功体験、思考パターンから生まれる「自分の常識」という基準が形成されているからです。
経営者ご自身の常識と「社員の常識」が異なれば、お互いが話していることを簡単に理解し合うのは難しくなってしまうのは仕方がないことです。言葉は、伝える手段ではありますが、組織を動かす力そのものではありません。経営者が考えるべきは、「話さなくても伝わる組織」をどう作るかです。
「話さないと伝わらない」から、「話さなくても伝わる」状態へ移行するためには、「組織の共通認識」を言語ではなく、仕組み・習慣・人事制度によって整えていくことです。例えば、価値観・行動指針を明文化し、採用・評価・昇格に一貫させる、重要な行動に対して「見える化」「仕組み化」を行う、「伝えたつもり」を防ぐ、確認ループを設けるなどです。
経営者の人を信じたい気持ちは尊いものです。しかし、信じるだけで任せるのは「無責任な丸投げ」と紙一重です。信じるからこそ、伝わる仕組みを整えることが必要です。任せるからこそ、正しく解釈される構造を用意すべきです。
「仕組みと思考の入れ替え」が、組織の信頼性とパフォーマンスを引き上げる鍵となります。
伝わらないのは、相手の理解力の問題ですか?
自社の情報伝達の仕組みに問題はありませんか?