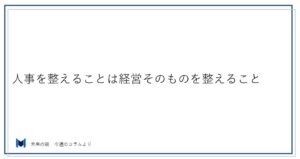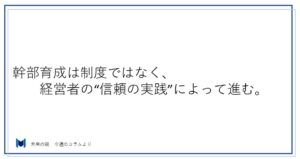第135号:人材不足を突破する唯一の方法
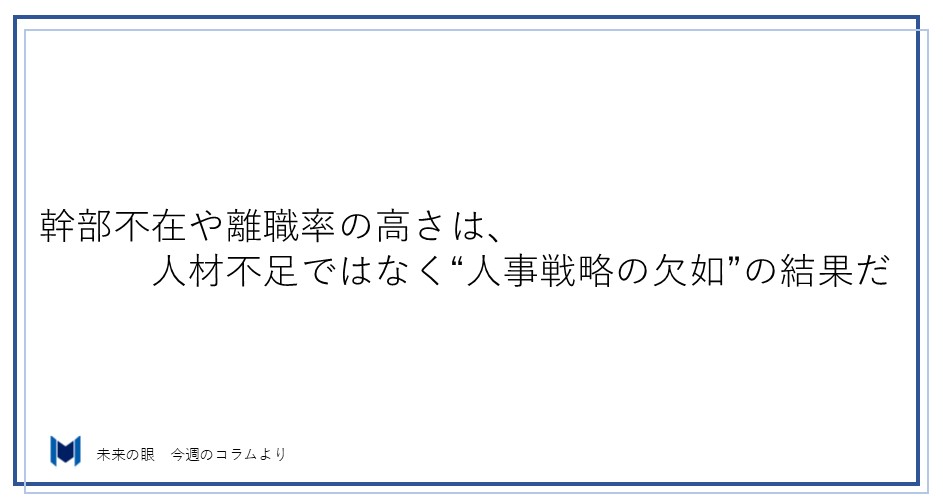
経営者を直撃する「人が足りない」という現実
「採用をしても応募が来ない」「せっかく採用しても定着しない」「幹部候補が育たない」。これらの人材不足に関する問題は一部の業界だけの話ではなく、多くの中小企業が直面する共通課題です。数字を追う経営者にとって、売上や利益の伸び悩みと同じくらい切実に響いているのが「人がいない」という現実です。
厚生労働省のデータによれば、日本の労働人口は今後も減少が続く見込みです。さらに働き手の価値観は多様化し、昔のように「入社したら長く勤める」という前提は成り立たなくなっています。こうした構造変化の中で、人材不足は単なる一時的な採用難ではなく、企業経営の根幹を揺るがす問題へと変貌しているのです。
人材不足が起きる背景
敢えて説明するまでもありませんが、「少子高齢化」、「働き方の多様化」、「ミスマッチによる早期離職」などがその背景です。出生率の低下により若年層が減り続け、高齢化が進行しています。その結果、採用市場そのものが縮小し、優秀な人材を確保する難易度は年々高まっています。特に地方では若者の流出も重なり、慢性的な人手不足が顕著です。
そして、副業解禁やリモートワークの普及により、社員は「会社に縛られず働く」選択肢を手にし始めました。経営者が従来型の働き方を前提に制度を運営していると、社員はより柔軟な環境を求めて離職してしまいます。
こうした状況の中で、「とにかく人を採る」ことを優先すると、入社後に期待とのギャップが生じ、早期離職を招きます。これにより採用コストは無駄になり、現場は常に人手不足が解消されない状態に陥ります。
人材不足が経営に与える影響
まず、求人広告や紹介会社への依存が増え、1人採用するためにかかるコストは年々上昇しています。しかし定着しなければ、その投資は回収されません。
また、人が足りないために一人ひとりの負担が増え、業務品質の低下やサービスの劣化を招きます。顧客離れが進めば、売上や利益の減少につながります。
現場対応に追われる社員には育成の余力がなく、幹部候補が育ちません。社長が細部まで意思決定を抱え込み、組織は拡大の壁を超えられなくなります。
人材不足の本質的な原因
経営者の多くは「人が足りないのは外部環境のせいだ」と考えがちです。確かに社会構造の影響は大きいものの、経営者の姿勢によって生み出されていることも否定できません。
・経営者が人事を後回しにしてきたこと
数字優先で制度設計を怠れば、人材は定着せず育ちません。
・人材をコストとしか見てこなかったこと
教育や育成を「費用」と考える限り、人材は資産化せず、常に採用依存になります。
・未来に必要な人材像を描いていないこと
「どんな組織をつくりたいのか」が曖昧なまま採用や育成を繰り返しても、戦略的な人事にはなりません。
事業戦略と人事戦略の統合が突破口になる
ここで強調すべきは、事業戦略と人事戦略が切り離せないということです。「新規事業を展開する」と掲げながら、挑戦に報いる評価制度がなければ、誰もリスクを取ろうとしません。「地域密着で顧客を守る」と言いながら、地域の人材を採用・育成しないのでは、看板倒れになります。
事業の方向性を決めたら、その実行主体となる人材像を定義し、採用・育成・評価・給与に一貫して反映させる。ここに初めて、人材不足を突破口に変える道が見えてきます。
人材不足を“外部要因”と片付けて、5年後も同じ問題を抱え続けようとしていませんか?