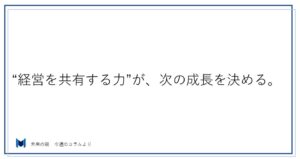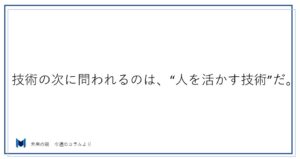第142号:経営者の無意識がつくる「育たない会社」の真実
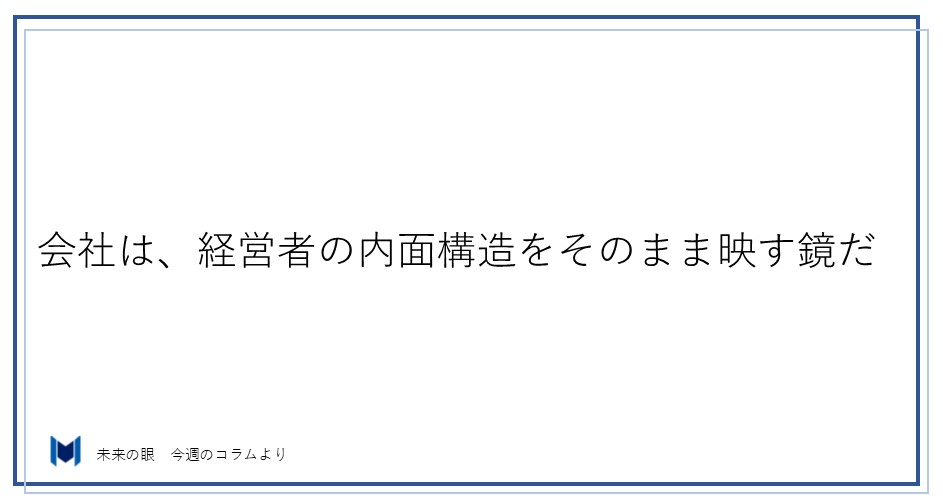
人を育てられない会社はなぜ生まれるのか──経営者の無意識がつくる構造
経営者の多くは、ある時期から同じ悩みにぶつかります。人を雇っても育たない。任せたいのに任せられない。幹部が自ら動かない。努力しているつもりなのに、組織は思うように伸びていかない。それは決して、社長の責任ではありません。
むしろ、会社をここまで育ててきた「強さ」が、次への成長を止めているのです。経営者の中にある、無意識の構造が人の成長を抑え込んでいるのかもしれません。
経営者の「成功体験」が組織の限界を生む
多くの経営者は、その事業の成長のためにスピードと即断力を磨いてきたのではないでしょうか。経営者が最前線で動き、現場を把握し、営業も開発も自分が決める。そのスタイルこそが成功の原動力となり、会社を軌道に乗せてきました。
ところが、同じ成功パターンが、一定の規模を超えた瞬間に限界へと変わります。トップがすべてを決める構造のままでは、人材が「考える前に待つ」ようになってしまいます。幹部は「社長の意図を読む」ことに慣れ、社員は「正解を探す」ことを学びます。
この無意識の連鎖こそが、組織の自律性を奪っていきます。
経営者は頭では理解しています。
「任せなければいけない」「人を育てなければ持続しない」。しかし、心のどこかでこうも思っているのです。「自分がやった方が早い」「任せると失敗するかもしれない」。この小さな不安が、会社全体の成長速度を止めてしまうのです。
任せたいのに任せられない “見えない壁”
経営者は頭では理解しています。「任せなければいけない」「人を育てなければ持続しない」けれど、「自分がやった方が早い」「任せると失敗するかもしれない」という小さな不安の存在を知っています。
過去に人を信頼して裏切られた経験、任せた結果うまくいかなかった記憶、それらが積み重なり、「もう失敗したくない」という防衛本能が働きます。脳は、自分の心が傷つかないように現実を都合よく解釈しようとします。
そのため経営者は、「今はタイミングじゃない」「まだ幹部が育っていない」とやらない言い訳を作ることができます。自分を守ることは悪いことではありません。それは、過去の痛みから学んだ知恵です。
変化を起こす第一歩は、「自分を責めないこと」
経営者ほど、自分に厳しい存在はいません。「もっとできたはずだ」「自分の判断が遅れた」と、誰よりも先に自分を責めてしまいがちです。しかし、その完璧主義が、変化を遠ざけることがあります。経営とは、常に不確実な状況の中で最善を選び続ける営みです。
任せられなかったことも、育てられなかったことも、当時の最適解だったはずです。大切なのは、過去を責めることではなく、その“判断の背景”を理解し、次の設計に活かすことです。変化の第一歩は、自己否定ではなく、自己理解から始まります。
小さく任せて、成功を体験する
経営の現場では、「任せる」と「放り投げる」は似て非なる行為です。任せるとは、責任の移譲ではなく、判断基準の共有です。
まずは、限られた範囲で意思決定を委ね、そのプロセスを共に検証していくことです。経営者自身が「この判断は任せても大丈夫だ」と確信を持てた瞬間、組織の空気が変わります。社員は、信頼という目に見えないメッセージを敏感に受け取るのです。任せるとは、信頼の「投資」です。
経営者の変化が、会社の構造を変える
経営を変えるとは、仕組みを整えることだけではありません。今回ここでお伝えしているのは、経営者の「心の構造」を変えることです。
社員を信じるとは、コントロールを失うことではなく、力を分かち合うことです。その理解が生まれたとき、会社は本当の意味で動き出します。
社員が自ら判断し、失敗を恐れず挑戦する。
幹部が経営の意図を汲み取り、事業の未来を共に考える。
こうした状態が生まれると、人材は「コスト」から「資産」へと変わります。そして、経営者は自分の時間を「現場対応」から「未来設計」へと使えるようになります。
「任せられない」という言葉の裏に、何を失うことを恐れていますか?