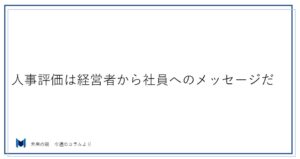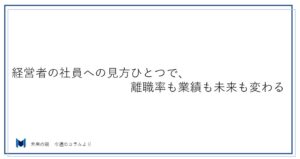第132号:なぜ、幹部は育たないのか?
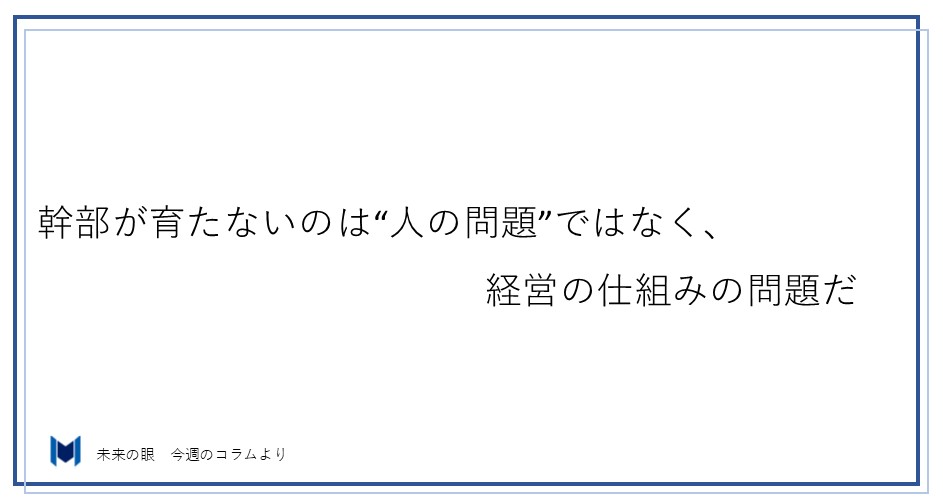
経営幹部が育たない会社
「任せても判断できない」「視野が狭く現場の延長線でしか考えない」「結局、最後は社長に相談してくる」。このような状況に心当たりがある経営者は少なくないです。しかし、幹部が育たないのは個人の資質や努力不足の問題だけではありません。
幹部が育たないことで生じる深刻なリスク
幹部不在の最大のリスクは、経営者がすべてを抱え込み、意思決定のスピードが鈍化することです。例えば、売上が拡大し社員数が増えても、社長が人事も営業も最終判断を担っていれば、やがてボトルネックとなります。成長期に差しかかった企業ほど、この「社長依存型経営」の限界に直面します。
また、幹部が育っていないと事業承継にも支障が出ます。後継社長に引き継いだとしても、頼れる幹部がいなければ、新社長は孤立しやすく、組織は混乱します。つまり、幹部不在は単に「日々の経営が大変になる」だけでなく、会社の未来そのものを危うくするのです。
幹部が育たない5つの背景要因
幹部が育たない理由は、本人の能力不足だけではありません。実は、経営者のリーダーシップスタイルや人事制度の設計の仕方、さらには組織文化のあり方に根本的な原因が潜んでいます。
- 経営者のリーダーシップスタイル
トップダウン型が強すぎれば、幹部候補は「指示待ち優秀社員」にしかなりません。逆に「任せきり」の放任型では、方向性を見失い、責任を放棄する人材が生まれます。
幹部を育てるには、「裁量と責任を段階的に与える」デザインが欠かせません。つまり、経営者自身が育成の意図を持ってリーダーシップを発揮できるかどうかが重要なのです。
- 幹部候補の選抜基準の誤り
多くの企業では、「勤続年数」「営業実績」が幹部選抜の主な基準になっています。もちろんこれらは一定の評価に値しますが、それだけでは不十分です。
経営幹部に必要なのは、戦略性・俯瞰力・組織を動かす影響力です。もしその視点を欠いたまま昇進させれば、本人も周囲も「昇進=ゴール」と錯覚し、学びを止めてしまいます。結果として「役職はあるが経営を担えない幹部」が量産されます。
- 成長の「場」を与えていない
人は場によって成長します。しかし現実には、幹部候補に重要な商談を任せず、経営会議にも参加させない。外部の研修や異業種の学びの機会も制限してしまう企業は少なくありません。
「育てたい」と言いながら、日常業務を変えず、責任を任せない。これでは幹部は育ちません。経営者に求められるのは、失敗を恐れずに「挑戦の場」を与える覚悟です。
- 時代に合わない「古い幹部像」
幹部の理想像がアップデートされていないことも問題です。かつては営業力や現場統率力が重視されました。しかし今の経営幹部には、ITリテラシー、データ活用力、意思決定、リーダーシップなど、新しい能力が欠かせません。
過去の基準にとらわれ続ければ、企業は市場のスピードに取り残されます。幹部像を再定義し、次世代型リーダーを意識した育成が必要です。
- 人事制度の一貫性不足
幹部育成の最大の土台は人事制度にあります。評価・給与・育成・採用がバラバラに設計されていると、社員は「この会社はどんな人を幹部にしたいのか」を理解できません。
制度は単なる管理の仕組みではなく、経営が社員に示す「未来の物語」です。評価制度で重視するポイント、給与制度で報いる姿勢、研修制度で与える学びが一貫して初めて、社員は「この道を歩けば幹部になれる」と信じるのです。
幹部育成を進めるために経営者ができること
幹部が育たない背景には、経営者のリーダーシップの偏りや、選抜基準の誤り、育成の場の不足、時代に合わない幹部像、人事制度の不整合といった複合的な要因があります。これを解決するには、経営者が意図的に「育成の仕組み」を整えることが欠かせません。
まず、幹部候補には意思決定の場を与えることです。会議や重要案件で一部でも判断を委ね、その結果を振り返る習慣が必要です。次に、幹部に求める資質を言語化し、評価制度に組み込むことで、社員が「何を伸ばせば幹部になれるか」を理解できます。
また、評価・給与・育成・採用を一貫した物語として統合し、採用段階から「この会社の幹部像」を明確に示すことも重要です。さらに、過去の基準にとらわれず、ITリテラシーや変化対応力など新しい能力を取り入れ、幹部像を時代に合わせてアップデートする必要があります。
幹部育成は放置しても進みません。経営者が覚悟を持って制度と場を設計することで、未来を担うリーダーは初めて育つのです。
あなたの会社は、評価・報酬・育成・採用は一つのストーリーになっていますか?