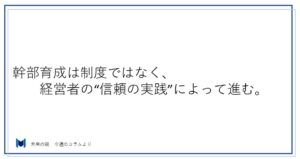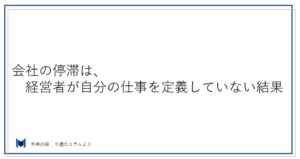第137号:社員研修で成果を出せない経営者が陥る3つの罠
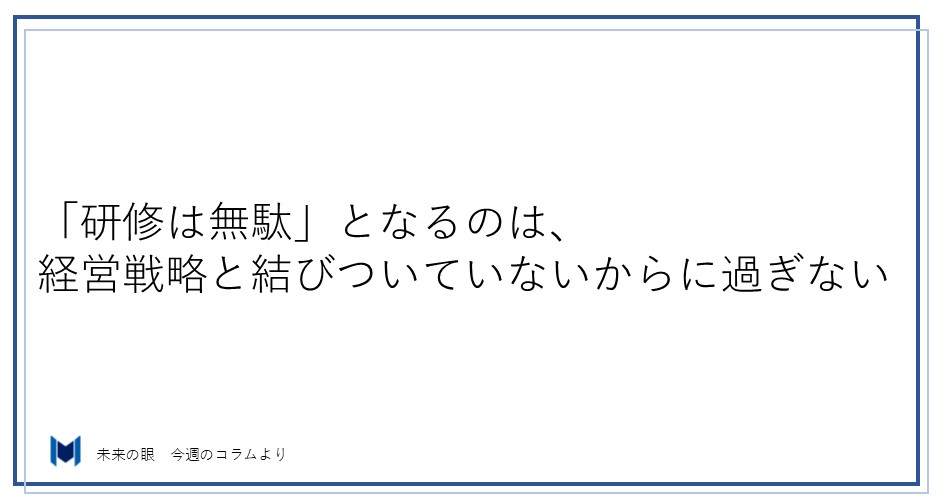
研修は本当に意味があるのか?経営者が直面する永遠の問い
取引銀行からの紹介で「専務からうちの会社の役にたつから参加してきてと、言われました。研修には参加ましたが、内容はうちの会社には合わないと思いました。お付き合いだから仕方がないんですけど…」と話してくれたのは、人事部の方です。
「せっかく外部研修に送り込んだのに、現場では全く変わらない」、「社員に学ばせても数日後には元に戻っている」これらは、多くの経営者が抱える共通の不満です。
ある調査によれば、中小企業で研修を実施した後に「効果があった」と答えた経営者はわずか3割程度です。残りの多くは「投資に見合う効果を感じない」と答えています。研修が「意味があるのか」という問いは、現場感覚として決して的外れではありません。
問題は研修そのものではなく、経営戦略や人材方針と切り離され、単発のイベント化していることにあります。
なぜ研修が成果につながらないのか
・現場との断絶
営業現場では顧客との対応に追われる日々。そこに「理論中心の座学研修」を導入しても、社員からは「机上の空論」と受け止められます。学んだ
内容が日常業務に結びつかないと、行動変容は起きません。
・経営戦略との乖離
ある製造業の経営者は「幹部候補を育てたい」と言いながら、コストを抑えるために汎用的なビジネス研修を導入しました。結果として、現場に必
要な「意思決定力」や「部門を率いる力」は育たず、時間と費用だけが消えました。これは「経営課題と研修内容のミスマッチ」の典型例です。
・フォロー体制の欠如
研修後に上司が「で、何を学んだの?」と一言聞くだけで終わっていないでしょうか。人は一度学んだだけでは行動を変えません。振り返りや実践
の場を仕組みとして整えない限り、学びは現場に定着しません。
研修を“意味ある投資”に変える経営者の役割
・未来像を明確に描く
「3年後、どんな事業で勝負し、どんな人材が必要か」。この未来像を具体的に描き、言葉にできるのは経営者しかいません。社員は、経営者が示す未来の地図を見て、自らの成長を重ね合わせます。もしビジョンが曖昧であれば、研修も“点”で終わり、組織の方向性とは結びつきません。経営者が「未来像」と「今の研修」を接続することが、学びを組織文化に変える第一歩です。
・研修を経営課題に直結させる
研修は単なる学習イベントではなく、自社の業務課題を解決するための場にすることをお勧めします。例えば「営業成績が伸び悩んでいる」という課題があるなら、必要なのは一般的な営業理論の学習ではなく、自社の顧客層に即した提案方法を実践的に学び、現場で試す研修です。
あるいは、「幹部候補が意思決定に弱い」という課題を抱えているなら、ケーススタディだけでは不十分です。研修後に実際の会議で意思決定を担わせ、フォローする仕組みを組み込むことで初めて成果につながります。
このように、研修のテーマや内容は「経営戦略」や「現場の課題」と直結させなければ意味を持ちません。経営者が「自社の課題解決ためのために実施する研修」であることを明確にすれば、研修は社員にとっては「自分の仕事を良くするための武器」として受け止められるのです。
研修の真の価値は、社員の成長が業務改善に直結し、会社全体の成果を押し上げることにあります。
・社員に期待を明確に伝える
研修に意味を与えるのは研修そのものではなく、経営者の姿勢です。「とりあえず行ってこい」と言われれば義務感に終わりますが、「この研修を通じて、君にはこう成長してほしい」と伝えられれば、学びは自己成長と結びつきます。
とはいえ、経営者が社員一人ひとりに毎回直接こうした言葉をかけるのは現実的には難しいでしょう。そこで重要になるのは、「経営者の思いを仕組みに組み込む」ことです。
大事なことは、直接の声かけが難しくても、仕組みや場を通じて「会社はあなたに本気で投資している」というメッセージを伝えることです。
あなたの会社の研修は、経営課題と直結していますか?
形式的な“教育イベント”で終わっていませんか?