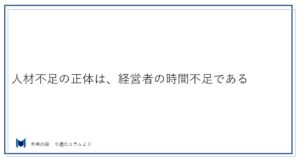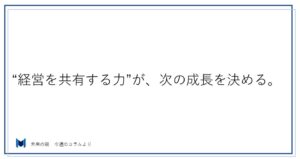第140号:視野が狭い社長ほど、“人がいない”と嘆く
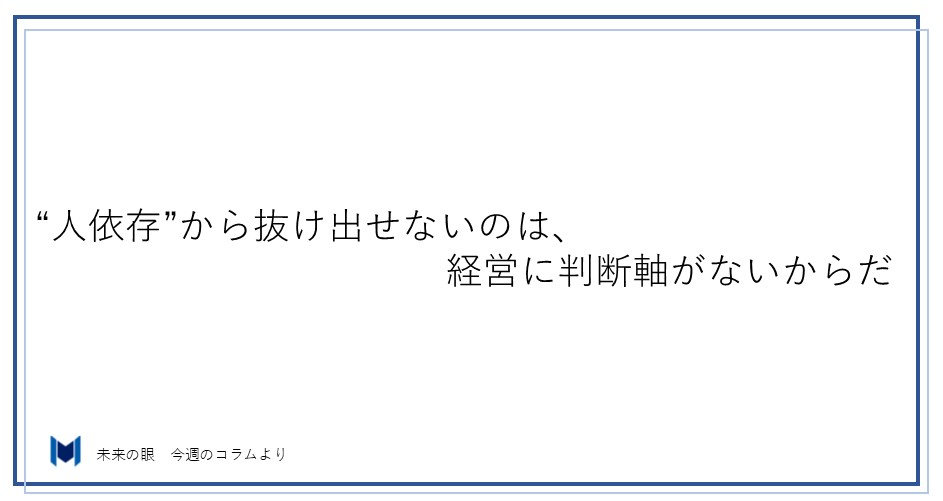
人がいないと仕事が回らない──人依存の業界構造を変える経営者の決断
どれだけ求人を出しても人が集まらない、採用しても数年で退職してしまう。結局、いつも同じメンバーで回し続け、限界の中で仕事を受けざるを得ない。そんな悪循環に陥っていませんか。
この問題は「人に頼るしかない経営構造」にあります。人材不足の根は、採用力の問題ではなく、仕組みの不在にあります。経営者がこの構造を変える決断をしなければ、どれだけ採用活動を強化しても、現場の疲弊は止まりません。
経営者の時間の使い方が、会社の未来を決めている
多くの企業が人依存の構造から抜け出せない最大の理由は、経営者自身が“現場依存体質”に陥っていることです。
創業時には、社長自らが最前線に立ち、誰よりも働いてきた。その姿勢が社員を鼓舞し、会社を支えてきたのは事実です。けれど、会社が一定の規模に達しても、同じやり方を続けると、社長の存在が「現場を止める要因」になってしまいます。
すべてを社長が判断しなければ進まない。重要な案件は結局トップに戻る。こうした状況下では幹部は育ちようがありません。つまり、“人がいない”のではなく、“社長しか動けない会社”を作ってしまっているのです。
属人化の罠──「あの人がいないと回らない会社」
もうひとつの問題は、仕事が属人化していることです。ベテラン社員が長年の勘と経験で仕事を回してくれる。確かにありがたい存在ですが、それが“再現性のない成功”であることを経営者は理解しておく必要があります。作業がマニュアル化されず、引き継ぎも曖昧なまま。新人は見よう見まねで覚え、離職すればノウハウが消える。
これが「人がいない」と言われる組織の正体です。「人材がいない」のではなく、「仕事の仕組みが人に吸い取られている」。再現性を失った組織は、どんなに採用を頑張っても疲弊し続けます。
「短期志向経営」が人を育たなくする
さらに深刻なのは、数字中心の“短期志向”です。売上、利益、キャッシュフロなどといったように、これらを追うこと自体は当然ですが、あまりに短期成果に偏ると「教育」「仕組みづくり」「人材育成」は“コスト”と見なされ、後回しにされます。
その結果、現場は常にギリギリの人数で回し、社員は疲弊し、成長の機会を失います。経営者は「即戦力がいない」と嘆きますが、実際には“育つ時間を奪っている”のです。
つまり、人手不足とは、「人の時間を使い切った経営」の末路ともいえるでしょう。
仕組みが会社を救う──人を頼らず、仕組みに頼る経営へ
「仕組み化」と聞くと、冷たいマニュアルや型にはめるイメージを持つ経営者は少なくありません。しかし、本来の仕組みとは「人を縛るもの」ではなく、「人の力を活かすための舞台装置」です。
ある飲食業の社長は、長年現場のベテランに頼っていました。誰もが「あの人がいなければ仕事が回らないから」と、気を使いながら仕事をしていました。
ところが、その“あの人”が急に退職したいと言い出したことで、現場は大混乱となりました。なんとか人を採用したいと、焦っても人は採れません。社長はようやく「人が辞めたことが問題ではなく、個人に依存していることが問題だ」ということに気がつきました。
仕組みとは、人を置き換えるためのものではなく、人が輝くための秩序です。属人に頼らない環境が整えば、社員は自ら考え、幹部は判断し、経営者は未来に時間を使えるようになります。人手不足の時代に求められるのは、“人を増やす経営”ではなく、“人が育つ仕組みを持つ経営”です。
あなたの会社は、人がいないのではなく、“あなたがいないと動かない”会社になっていませんか?