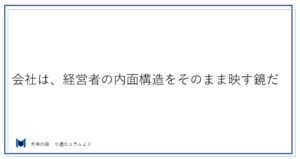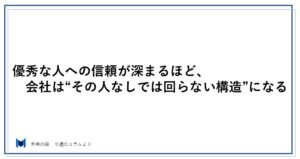第143号:技術が強いのに幹部が育たない企業の盲点
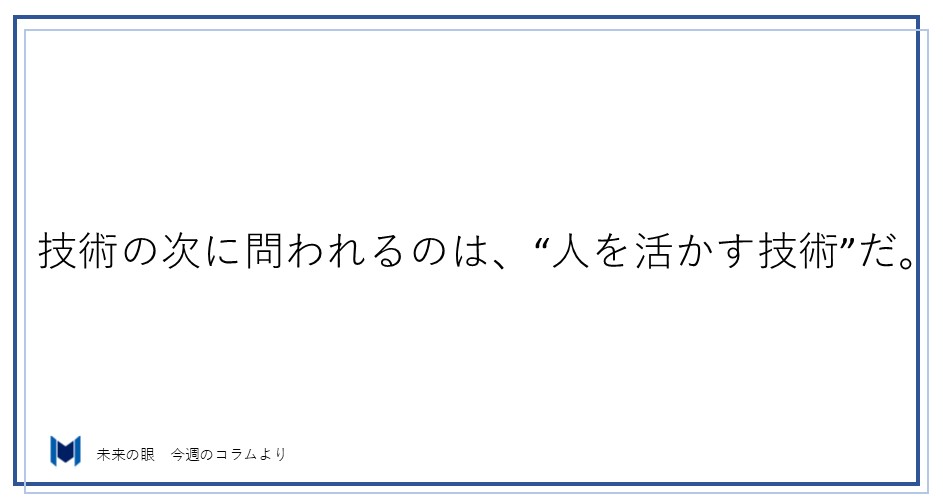
社員は優秀、でもチームが機能しないという現実
多くの企業が「技術こそ競争力の源泉だ」と信じて疑わない。実際、製造、IT、エンジニアリング、研究開発など、技術や専門知識を核に成長してきた企業は少なくありません。しかし、近年、その「技術力偏重」の経営が思わぬ壁にぶつかっています。
社員の技術力は高い。プロジェクト単位の成果も悪くない。しかし、なぜか組織全体が伸びない。そんなもどかしさを感じている経営者は少なくありません。
会議では専門的な意見が飛び交うのに、誰も「事業をどう成長させるか」を語らない。個々は優秀なのに、チームになると意思決定が遅れ、リーダーが育たない。「技術力や専門性で勝ってきた企業ほど、組織がうまく動かない」、これは偶然ではありません。
その背景には、技術偏重の人材育成構造という、見えにくい落とし穴が存在しています。
技術が強い企業ほど陥る「育成の構造ミス」
多くの企業は、「人を育てる=スキルを教える」と定義しています。特に技術や専門性で成長してきた企業ほど、教育や研修の中心が「技術指導」に偏りやすい傾向があります。しかし、この育成構造そのものが、人の成長を止める原因になっているケースが増えています。
1. 評価が「技術スキル」だけに縛られている
技術力を重視する企業ほど、評価基準が成果物中心になります。「どれだけ高度な技術を使いこなせるか」「どれだけ難しい課題を解決したか」。こうした指標は明確で測りやすい一方で、他者と協働する力や、判断力・リーダーシップが置き去りになります。
結果として、社員は「自分の専門領域を極めること」が目的化し、チームや事業全体を俯瞰する視点を失います。たとえ優秀な個人が集まっても、「組織としての成果」が上がらない理由は、ここにあります。
2. 「リーダーは自然に育つ」という幻想
多くの技術系企業には、次のような思い込みが根強く存在します。「優秀な技術者は、やがて自然にリーダーになる」と、しかし現実には、リーダーシップは別の筋肉です。論理よりも感情を扱う力、正解がない状況で決断する胆力、他者を動かすコミュニケーション。これらは経験と学習を通じてしか身につきません。
にもかかわらず、「現場で見て学べ」「時間が解決する」という強い思いから抜け出せず、「次世代幹部は育たない」「育成の不在は時間では埋まらない」という現実を無視してしまうことが多々あります。
3. 専門性の壁が「連携」を妨げる
専門性の高い組織では、部門がサイロ化しやすくなります。設計、開発、営業、製造、それぞれが自部門の成果を最優先し、他部門との連携が後回しになります。すると、意思決定は縦割りになり、変化へのスピードが鈍る。
経営が「連携せよ」と訴えても、「他部署は分かっていない」「自分たちの方が正しい」と現場は認識します。この構造の根にあるのも、技術中心の価値観です。技術が正義である限り、組織は議論よりも正解探しに時間を費やし、結果的に事業スピードを落とします。
技術偏重の背景にある「経営の心理構造」
なぜ、この構造から抜け出せないのでしょうか。それは、技術中心企業の経営者自身が次のような信念を持っているからです。
1.「自分たちは技術で成長してきた」という成功体験
2.「技術を磨けば報われる」という職人気質の信念
3.「人を育てるのは自分の専門外」という無意識の線引き
これらは決して間違いではありません。むしろ、企業を支えてきた強みでもあります。しかし、事業が拡大し、組織が多層化するフェーズでは制約条件に変わるのです。
「教える」から「考えさせる」ことへ
では、どうすればこの構造を変えられるのか。鍵は、「技術を教える」から「技術を活かす人を育てる」へと、育成の定義を再設計することではないでしょうか。それは、「知識の獲得」から「判断の形成」にすることにより、「何を知っているか」ではなく「どう判断するか」を目的とすることです。
事業環境が変化する中で、技術そのものよりも、「どんな場面で何を優先するか」を判断できる人材が、組織を支えます。これは、リーダーになる準備をさせることにも繋がります。小規模な意思決定を繰り返すことにより、その精度を高めていくことができるでしょう。
技術は企業の資産です。しかし、それを価値に変えるのは、技術ではなく“人”です。だからこそ、経営者に問われているのは、「次の技術」ではなく「技術の次にある成長の絵」を描けるかどうかです。
社員が技術を通じて事業を動かし、組織が技術を超えて価値を生み出す。その状態こそが、“技術系企業が本当の意味で人材リッチになる”瞬間です。
あなたの会社は、技術が強みだったはずなのにいつの間にか時代から遅れをとっていませんか?