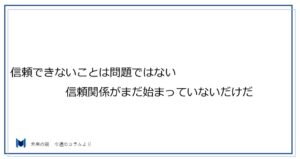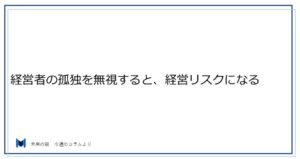第117号:経営者が見逃しがちな幹部社員の評価基準
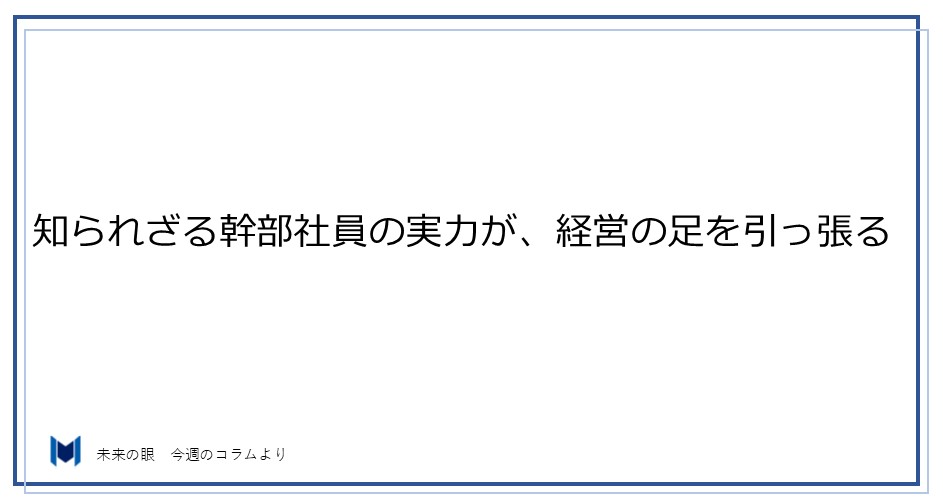
「うちの幹部たちは、よくやってくれているよ。」と語ってくれたのは、とある経営者です。幹部社員の役割や成果基準などについて、質問を重ねると歯切れが悪くなってしまいました。幹部社員は、経営者の右腕として現場を束ね、経営を左右する重要なポジションですが、その実態を正しく把握できている経営者は意外なほど少ないのが現実です。
特に中堅・中小企業に幹部候補の多くが「長く勤めている」「現場をよく知っている」「創業期から苦楽を共にしてきた」など、情的な評価で昇進しているケースが見られます。それ自体は悪いことではありませんが、「勤続年数」「現場理解」「人情」と幹部社員として「結果を能力」はイコールではありません。年数を重ねた幹部社員が、必ずしも組織成長に貢献しているとは限らないという厳然たる事実に、どれだけの経営者が向き合えているでしょうか。
さて、幹部社員の経営に関する能力が把握できないことで発生する最大のリスクは、経営判断の誤りです。たとえば、「あの幹部なら任せておけば大丈夫」と思い込んで新規事業を委ねた結果、現場での実行が伴わず、プロジェクトが頓挫してしまう。上司に見せる顔と部下に対する接し方があまりにも違い、退職者を量産させている。このような状況は、幹部の能力を見誤ったことによるものです。
幹部の能力を正確に把握できない理由は、まず、経営者が幹部社員への期待と現実を混乱していることがあります。「この人ならもっとできるはず」「厳しい時代だから結果がないのは仕方がない」と、期待や温情をかけすぎてしまうことがあげられます。特に創業期からの付き合いなど、ともに過ごしている期間が長い幹部ほど、情に左右されてしまいます。
次に、幹部社員それぞれの業務は多岐に渡り、複雑化しています。そのため、評価軸が不明確となりやすいという点があります。また、その仕事は、部門の管理、部下育成、問題解決など定量化しにくい側面を多く含んでいます。結果として、評価が主観的になりやすく、「なんとなくよくやっている気がする」という曖昧な把握に流れてしまうこともあります。
そして、経営者自身が幹部のふるまいに惑わされてしまうことがあります。日常的に接する機会が多く、話がうまい、経営者に対して忠実に見える幹部ほど、高評価を得やすいことがあります。その人物が現場で部下から信頼を得ているか、チームをまとめ上げているか、は見極めなければなりません。
「幹部の成長が、会社の成長を左右する」とよく言われますが、それ以前に、幹部の本当の力を見抜けなければ、育てることすらできません。経営者が幹部の能力を見誤れば、企業の未来は大きく揺らいでしまいます。
幹部社員の能力を正しく把握するためには、本人の自己申告だけでは偏りがでやすいため、現場の声を吸い上げる仕組みも重要です。あるいは、以前のコラム「第33号:成長し続ける企業のずるい人材評価術」でも書いたように、外部機関を活用することも有意義です。
そして、幹部の役割と成果を明確に可視化する評価基準が必要です。特に、幹部には「人を動かし、組織を前進させること」が求められます。「実務対応」「問題課題発見(対応)」「主導力」「人材育成」などというように、自社で期待している役割と成果に対する基準値を策定することです。
最後に、経営者自身が評価する眼を鍛えることが最も重要なことです。幹部との定期的な面談や業務報告だけでなく、「本当に必要なのは、幹部が日々感じている葛藤や、未解決の課題、部下との関係性など、「見えない情報」を共有できる空間です。この対話が生まれることで、幹部のマネジメント資質や思考の癖、判断の軸が初めて浮かび上がります。
また、人材を「資産」としてとらえる発想も今後ますます重要になっていきます。給与や人件費を「コスト」と見るか、「将来利益を生む投資」と見るかで、経営の視点は大きく変わります。幹部社員もまた、単なる管理職ではなく「企業価値を高める人材」として位置づけなければなりません。
どれだけの権限を委ねるか、どれだけ育成に投資するかは、その幹部が「企業にもたらす価値」と比例するのかもしれません。幹部育成は単なる人事の仕事ではなく、経営そのものなのではないでしょうか。