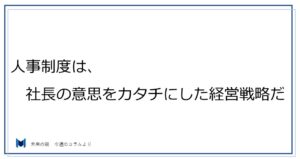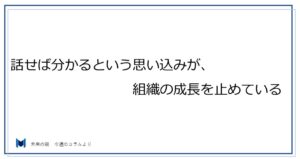第126号:“右腕”が育たない会社の盲点
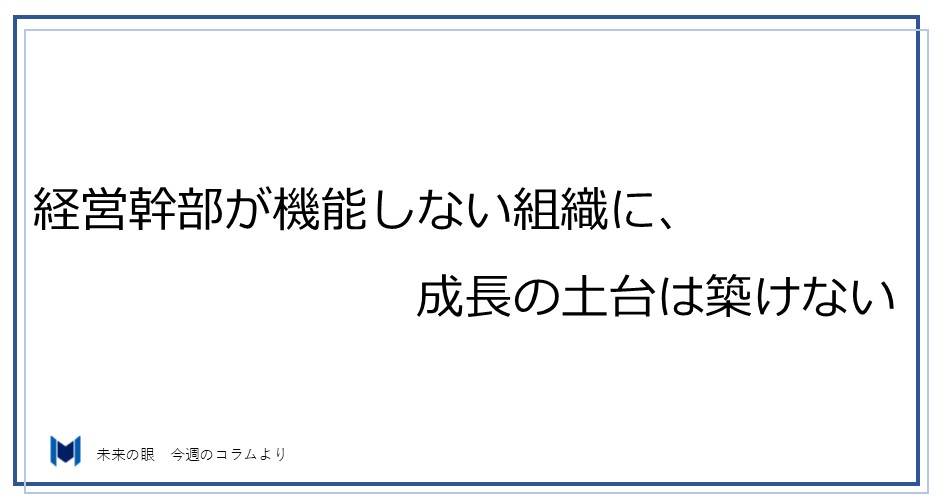
「関連会社のトップにうちの幹部社員が泣きついたみたいで、ちょっと厄介なことになっています。幹部社員たちの考えていることが、ばらばらです。自分の利益を優先し、あえて社内を混乱させているので、困っています。」と、数社を巻き込む事案が発生しまったとご報告を頂きました。
企業が成長するにつれて、経営者の目が行き届かない領域は増えていきます。それを支えるのが幹部ですが、経営幹部チームの機能不全に悩む企業が少なくありません。幹部社員に対して、「頼りない」、「責任感がない」、「自分のこと、自部門のことしか考えない」といった不満を抱えている経営者の声を聞きます。
このような課題を解決する視点の1つを以前のコラム「第117号:経営者が見逃しがちな幹部社員の評価基準」で紹介していますが、今回は別の観点からこの課題について考えていきたいと思います。
中小企業やオーナー企業においては、幹部の役割が曖昧であるケースが見られます。経営者が「信頼して任せている」と口にする一方で、幹部は「何をどう判断してよいかわからない」「結局、最後は社長が決めるから…」と、受け身の姿勢になっていることがあります。
右腕といえば聞こえはよいですが、経営者のいうことをこなせる「上級プレイヤー」であることが大半です。このような状況になってしまうのは、役割と責任の定義が不明確であり、期待値が共有されていないことに起因しています。
そのため、任された仕事の範囲や、どこまでが自分の権限なのかが見えず、主体的に動くことは難しい状態にあります。これでは、いつまで経っても「経営のパートナー」として成長することができませんし、組織の機能を高めていく上でもそれを妨げる存在となってしまいます。
幹部社員たちのチームが機能しないもう一つの要因は、「個の優秀さ」と「チームの強さ」は必ずしも一致しないということです。むしろ、成果を出してきた個が集まるほど、それぞれが自分のやり方や成功体験に固執しやすくなり、方針や優先順位をめぐって衝突しやすくなります。
経営者が「どちらの意見が正しいか」を判断するスタンスを取ってしまうと、幹部たちは徐々に発言を控えるようになり、意見のぶつかり合いではなく「空気を読む」関係性が生まれてしまいます。表面的には平和に見えても、深いレベルでの信頼や共通理解が形成されないまま、組織は機能不全に陥っていきます。
ですから、経営幹部が本当の意味で「経営に参加する」ためには、単なる部門責任者の意識を超え、「この会社の未来を共につくるパートナー」としての覚悟が必要です。その覚悟が生まれるかどうかは、幹部本人の資質だけでなく、経営者の姿勢にも大きく左右されます。
会社の未来を築く上での経営課題、悩みを幹部と共有し、対話することで、幹部の視座が変わります。「自分も経営に関わっている」という自覚が芽生えていきます。時には、経営者が思っても見なかったようなことを、考えている幹部社員がいることは珍しいことではありません。
さて、幹部社員を経営パートナーへと導いていくには、経営者が期待している成果と基準を明確にし、その進捗を定期的に確認することが必要です。こうした過程を経ることは、経営幹部の「判断の軸」、「責任の範囲」を養うことにつながります。結果的に、幹部社員を経営パートナーへと育成することとなります。
ところで、こうした幹部個人の意識や役割の重要性を語るとき、忘れてはならない視点があります。それは「幹部が一人で動いても、会社は前に進まない」という事実です。幹部がどれだけ優秀であっても、それが「個別最適」に留まっていれば、企業の成長は頭打ちになります。
経営者が幹部社員を経営パートナーへと導くには、「幹部がまとまり、組織が一つの意思で動くこと」の重要性を認識させることが鍵です。幹部同士の方針が食い違えば、現場は混乱し、従業員は不信感を募らせます。やがて「言っても無駄だ」という諦めが組織に蔓延し、競争力を失っていきます。
経営幹部を「企業の未来を共に背負う覚悟を持った対等な同志」と見なし、「対話の習慣」「共通の目的」「明確な役割分担」を支える仕組みを持つことが必要です。こうした経営幹部を育成していく設計があって初めて、幹部チームは一時的な関係性を超えた「経営の推進力」として機能するのです。
経営幹部は、経営の右腕ですか? 「代わりに動く手足」になっていませんか?