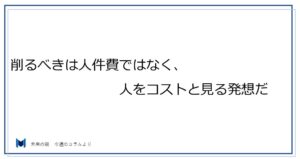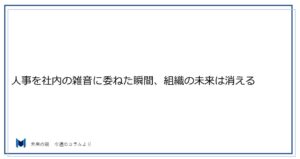第129号:人事は「制度」ではなく「未来の設計図」がなければ機能しない
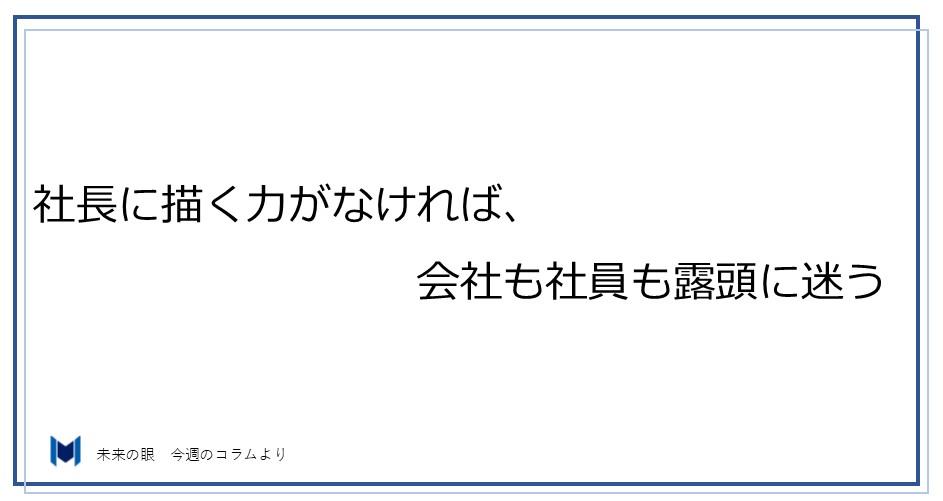
■社長にしかできない仕事とは──未来を描く力が人材戦略の起点になる
「大野さん、意思決定は部長でも役員でも副社長でもできるんですよ。でもね、未来を決めることは社長にしかできないんですよ。」と語ってくださったのは、交通インフラに新たな活路を見出そうと奮闘している会社の経営者です。
多くの経営者が、「忙しすぎて、自分がいなくても回る会社にしたい」という思いを抱えながらも、日々のオペレーションや現場対応に追われているのが実情です。クレーム処理、人材採用、売上の管理、システムの不具合対応など、どれも一見すると「社長がやらなければならない仕事」に見えますが、それらは本当に「社長にしかできない仕事」なのでしょうか。
結論からいえば、答えはNOです。多くの業務は社員に委ねることができますし、むしろ社長が細部に入り込みすぎることで、社員の成長機会を奪われてしまいます。では、経営者でしかできない、組織にとって最も重要な役割とは何でしょうか。それは、未来を描くことです。
■なぜ未来を描くことが、人事戦略の要になるのか?
どれほど優秀な人材を採用しても、どれほど現場が努力を重ねても、「この会社は何を目指しているのか」が曖昧であれば、やがて組織は空中分解してしまいます。経営理念やビジョンが存在する企業であっても、現実的で具体的な中長期の方向性や戦略が描かれていなければ、現場は迷い、マネージャーは疲弊し、優秀な人材ほど離れていく傾向があります。
「未来を描く」とは、単なる夢や理想を語ることではありません。市場環境や業界構造、人材動向などの変化を見据えながら、「自社はどこで勝負するのか」「どこに集中するのか」「どのような人材が必要となるのか」を構想し、組織全体にその方向性を明確に示す行為です。これこそが、社長にしか担えない、企業に最も大きなインパクトを与える仕事なのです。
■日常業務に追われる経営者が見失う“経営の本質”
しかし、多くの経営者が日々の業務に追われ、未来を描くことが後回しにしています。現場で起こるトラブルへの即応に追われるうちに、視野は短期的になり、今日の売上、今月の採用、来月のシフトといった“当面の課題”ばかりに意識が向いてしまいます。
その結果、経営者は「経営」から遠ざかり、組織は「目の前を回すだけの体制」となり、気づけば社員が育たず、組織力も停滞したまま年月が過ぎていくという事態に陥ってしまいます。このような状況では、人事施策もその場しのぎになりがちです。
「採用活動を強化しても人が定着しない」、「教育制度を整備しても成果につながらない」などいった問題の根本原因は、「未来の組織像が描かれていない」ことにあります。採用、育成、評価、配置といった人事の意思決定は、本来すべてが「どんな会社にしたいのか」という未来設計に基づいて行われるからです。
■未来から逆算して設計する人材戦略──組織づくりの出発点
たとえば、数年後に新規事業の展開を見据えているのか、既存事業の深化に注力するのか。少数精鋭の組織を目指すのか、規模拡大を前提とするのか。そのビジョンに応じて必要な人材像や組織構造はまったく異なります。未来の構想があるからこそ、人事施策は戦略性を帯び、制度や研修などが未来に向けた布石としての意味を持つようになります。
未来を描くことは、社員との信頼関係を築く行為でもあります。社員は、自分の役割がどこに向かっているのかが見えないと、不安を抱きやすくなります。特に優秀な人材ほど、自分が所属する組織の方向性や、自身の成長ストーリーに敏感です。
社長が明確なビジョンを持ち、「この会社はこう進む。その中で、あなたにはこの役割を期待している」と言語化できたとき、社員は「やらされている」から「共に創っている」という感覚へと変わり、主体性を持って動き始めます。
■経営者が描く“未来の地図”が、すべての人事施策を機能させる
人事施策を本気で機能させたいのであれば、その出発点は未来を描くことです。つまり、「この会社をどうしたいのか」「どんな組織にしていきたいのか」という社長自身の意思を明確にすることが最も重要なのです。制度や仕組みは後からいくらでも整えられます。しかし、そこに“未来への道筋”がなければ、全体の施策はちぐはぐなものとなり、効果は長続きしません。
社員に任せられる業務は増やしていけますが、「未来を描く」ことだけは、社長にしかできません。未来の解像度が高まれば高まるほど、人事は経営戦略と一体化し、組織は自律的に動き出します。社長の中にある“未来の地図”こそが、すべての人と組織を動かす源になるのです。
社員に「この会社はどこに向かっているのか」と聞かれて、即答できますか?