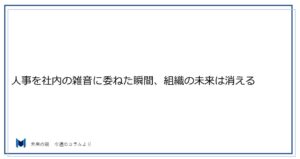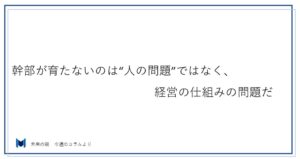第131号:人事評価制度を変えても社員が変わらない理由
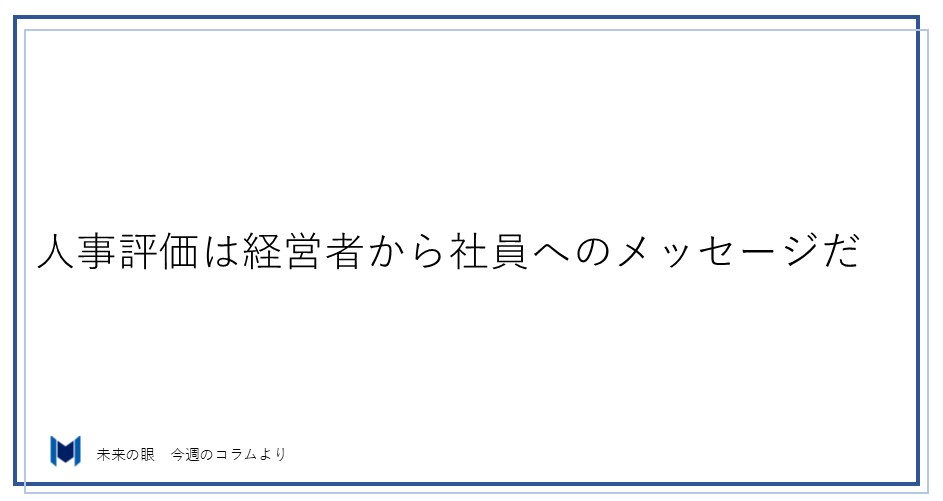
評価制度さえ整えれば、人は育ち、離職も防げる。
「公平に評価したい」「人が育つ会社にしたい」と評価制度を導入するとき、多くの経営者がこう語ります。評価制度を入れれば、「人に関する悩み」が減ると信じています。しかし現実は、人事評価制度を導入したのに、社員の不満が増え、優秀層が辞めていく企業が少なくありません。
原因は制度そのものではなく、「評価制度」が経営から切り離されていることにあることがあります。人事制度は、経営者から社員へのメッセージです。自社が勝ち続けるためには、社員に「どのような働き方」で「どのよう行動と結果」を求めているかを伝えるものです。
ところが、人事評価という手段だけが持ち込んでしまうために、基準が曖昧になり、不満を抱える社員が増えてしまいます。
人事評価制度は経営者の「翻訳装置」
人事評価制度は、経営者が描くビジョンを社員の行動と成果に翻訳する重要な仕組みです。「何を評価するのか」は、「会社がどこを目指しているのか」を示す最も強力なメッセージになります。
しかし、多くの中小企業では、制度設計が外部委託に丸投げされ、人事評価制度を導入することがゴールになっています。その結果、経営計画との接続が曖昧なまま評価項目が運用され、制度は形だけ残り、本来の機能を果たさなくなります。
現場を迷走させる「制度の孤立」
例えばA社は、公平な評価を目指して新たな評価制度を設計しました。外部コンサルタントが作成した詳細な評価シートと目標設定制度と面談を導入し、運用も順調に見えました。しかし半年後、「何を重視しているのかわからない」という声が現場から続出。
理由は明確です。
経営者が「この制度は何のために存在するのか」を全社に共有していなかったため、評価は単なる査定や給与分配の道具になってしまったのです。
この結果、制度は不信感を招き、上司陣も社員もうんざりしています。
バラバラ外注が生む一貫性の欠如
さらに、評価、給与、育成、採用を別々の専門家に発注すると、整合性は崩れます。評価が期待する行動と、育成で伸ばす能力が異なる、採用時の求める人物像と昇格要件が一致しない、このような現象はあちらこちらで起きています。
たとえば、採用では「挑戦する人材」を求めているのに、評価では「現状維持型の安定志向」を高く評価する。このような矛盾は、社員の混乱と離職を加速させます。
制度の前に整えるべきは“経営の物語”
評価制度の導入によって、社員お手間と労力が増えた上にやる気まで失ったという企業は数えきれないほど存在しています。
人事評価制度を導入すれば、社員が勝手に成果を上げてくるわけではありません。そこには、必ず会社をどこに導きたいのかという経営者の意志が必要です。それが明確になっていれば、評価制度が戦略的な組織成長を下支えする装置と機能していきます。
人事制度を構築する前には、経営者は社員に語るべき物語があります。私たちはどの市場で勝ち、どんな価値を生み出していくのか。その物語が納得を生み、基準を生かし、事業を成長させる原動力へと向かわせていくことになります。
もし今、評価制度に物足りないと感じているなら、評価項目を増やす前に、経営者にしかできない物語を研ぎ澄ませてください。評価は人を裁くためではなく、組織の未来を生むためにある。その当たり前を実装できている会社は、例外なく強いです。
評価シートの項目は、経営者が望む人材像と一致していますか?