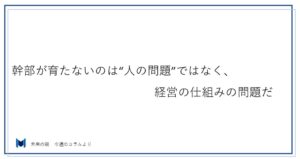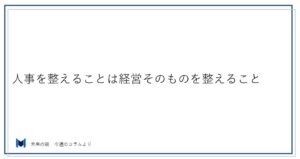第133号:人が辞める会社 VS 人が育つ会社
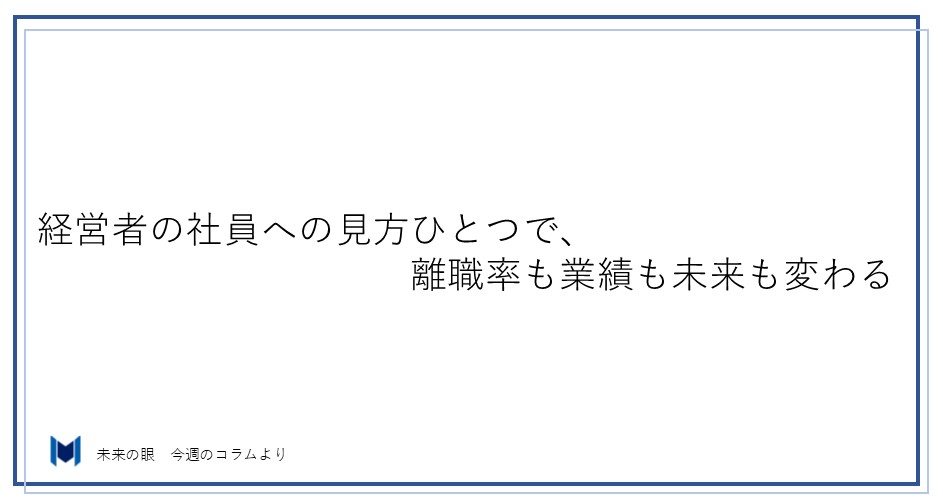
社員を大事にする経営と、短期志向の経営──中小企業の未来を左右する分岐点
経営者にとって、社員は「未来を担う資産」なのか、それとも「目先の数字を守るための労働力」なのか。この視点の違いが、企業の持続可能性を大きく左右します。
多くの中小企業の経営者が頭を悩ませるのは、「人が定着しない」「幹部が育たない」「採用コストばかり増える」という現実です。その背景には、社員を大事にする経営と、短期的な成果ばかりを優先する経営の姿勢の違いがあります。
短期志向経営が生まれる背景
短期志向的な経営では、短期利益を優先する。特に中小企業は資金繰りや取引先からの圧力に直面しやすく、「今期の利益」や「目先のコスト削減」が最優先課題となりがちです。その結果、人材は「将来への投資対象」ではなく「費用削減の対象」として扱われてしまいます。
また、「育てても辞めるのではないか」「教育投資が直接利益に結びつかないのでは」という不信感が、育成や研修を後回しにする心理を生みます。社員の成長意慾を無視し続けた結果、離職率を上げているということもあります。
創業期に身を粉にして働いた経験を持つ経営者ほど、「社員も同じように頑張って当然」という思い込みに陥りやすくなります。この考え方が長期的な視点を欠いた経営判断を強化し、社員を疲弊させます。こうした経営者の価値観は、人材管理において非常に重要です。
社員を大事にする経営の条件
一方で、社員を大事にする経営は人材を「コスト」ではなく「会社の未来を生み出す資産」という考え方をしています。そこにはいくつかの条件があります。
- 長期的な人材投資の視点
教育研修やキャリア形成を「費用」ではなく「資産形成」として捉え、社員を育てることを経営戦略に組み込みます。 - 公平で納得感のある評価制度
成果に加え、行動や成長を評価し、社員が「努力が報われる」と感じられる仕組みを整えることで、組織への信頼と定着率を高めます。 - 社員を経営のパートナーとして扱う
単に作業だけを指示するのではなく、将来の展望を社員と共有し「社員とともに未来を築き上げていく」ことが組織や仕事に対する関りを深めていくことに繋がります。
短期志向経営と人材重視経営の結果の違い
短期志向経営では、社員は定着せず、採用・教育コストが膨らみ、ノウハウが蓄積しません。品質やサービスは安定せず、顧客からの信頼を失い、長期的には利益率も低下していきます。
対照的に、社員を大事にする経営は、経験や知識が組織に蓄積し、生産性や付加価値が向上します。社員満足度が顧客満足度に結びつき、業績は安定し、持続的に成長していきます。
本質は「資産視点」と「コスト視点」の違い
分岐点はシンプルです。経営者が社員を「資産」と見るのか、「コスト」と見るのか。資産と見れば投資対象となり、育成や制度設計は「未来を創る経営行為」となります。コストと見れば削減対象となり、短期的成果を優先するあまり、組織の基盤は弱体化していきます。
経営者が踏み出すべき次の一歩
人材不足や高い離職率に悩んでいる経営者の皆さんがやるべきは、「社員に対する見方」を見直すことです。社員を“労働力”として消費する存在と見るのか、「未来を共に創る仲間」と見るのか。その視点の違いが、組織の在り方を根本から変えます。
社員を大事にする経営は、理想論ではなく現実的な経営戦略です。短期志向経営から長期的な人材重視経営へと舵を切ることが、会社の未来を守る最も確実な一歩です。
10年後、今の社員があなたの会社を支えている姿をイメージできますか?