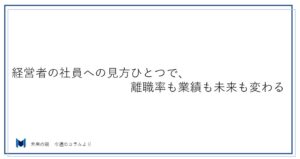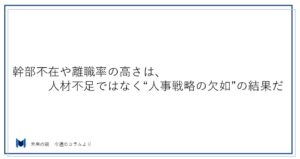第134号:数字優先の経営が失うもの──人事の盲点
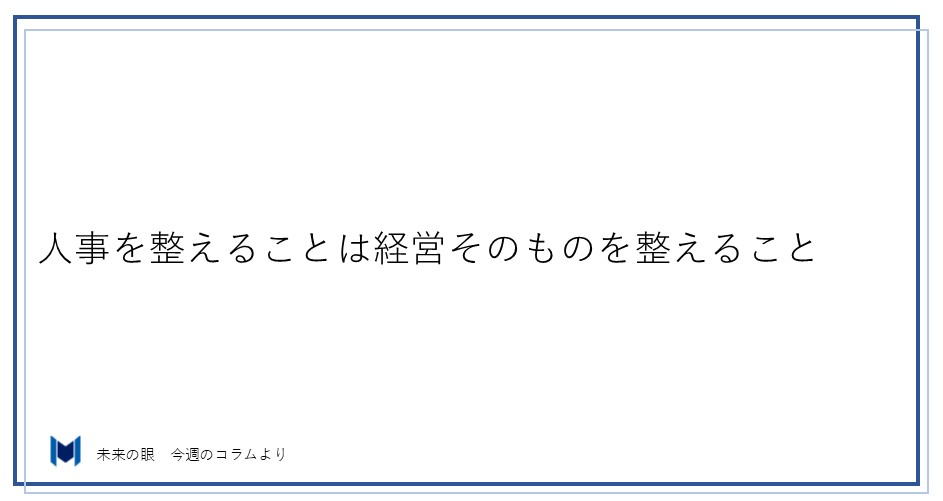
数字に追われ、人事が後回しにされる経営の現実
「新規顧客の獲得はいくら必要か」「資金繰りは大丈夫か」と、経営者の日常は数字に追われています。資金繰り表を開きながら、来月の売上をどう積み上げるかを考える。銀行への返済や取引先への支払いをどう回すかを調整する。これらは確かに喫緊の課題であり、避けては通れません。
しかし、その裏で忘れ去られている問いがあります。「社員は本当に定着しているのか」「幹部候補は社長不在でも意思決定できる力を持っているのか」「評価や給与の仕組みは、社員のやる気を引き出しているのか」これらは今期の決算には直結しないかもしれません。しかし軽視すれば、数年後に「採用してもすぐ辞める」「幹部が育たず社長が孤立する」という深刻な問題となって経営を直撃します。
短期利益を確保したい
売上や利益の数字は即座に確認でき、改善すれば翌月の決算に反映されます。しかし、人に施策は成果が出るまでに数年掛かることも珍しくありません。「来月の資金繰り」と「5年後の組織力」を天秤にかければ、どうしても前者が優先されるのは自然です。
経営者自身の経験
創業期に「制度がなくても必死に働いてきた」経営者ほど、人事施策を軽視しがちです。しかし、創業期のメンバーは経営者の目標や夢に賛同して集まった同志であり、どれだけ忙しくてもとも、進んで協力してくれたでしょう。あの頃のようにと、社員たちにも「自分と同じ覚悟」を求めてしまうことがあります。
社会構造の変化を軽視
昨今、人手不足が話題に上りますが、総務省の統計では2030年には日本の労働人口は6000万人を切る見込みです。採用市場の競争はすでに激化しています。しかし、日々の売上に追われる中小企業経営者ほど、この事態への備えを後回しにしてしまいがちです。
人材を軽視した結果
優秀人材は流出します。「この会社ではキャリアが描けない」と感じた社員は、迷わず転職します。年収が上がり、自分の成長が見込める会社を選ぶのです。昇進させても、意思決定の場を与えなければ、結局は社長があらゆる判断を抱え込み、「社長不在では会社が回らない」という状態になります。
飛躍したのに、組織が成熟しない
評価・給与・育成・採用がバラバラだと、社員への期待値があいまいになります。数年後には実現したいと思っている事業、今のビジネスをより広めていきたいと考えているのに、社長の想いを現実するのに必要な人材が分からないければ、組織は停滞します。
人材で競争に打ち勝つ
事業の方向性を描くとき、必ず「どの市場で戦うのか」「どのように競争優位を築くのか」を決めます。ところが、実行の主体者を決めずに物事を進めてしまうことがあります。それは、絵に描いた餅になります。
たとえば、新規事業を立ち上げたいなら、起業家的な発想やリスクを取れる幹部候補が必要となります。逆に、既存事業の深耕でシェア拡大を狙うなら、オペレーションを磨き上げ、粘り強く改善を重ねられる人材が不可欠です。つまり、事業戦略が定まれば、自ずと求める人材の資質・スキル・配置の方針が導かれるのです。
同じ商品は簡単に模倣されますが、組織に根付いた文化や人材の総合力は真似できません。圧倒的に強い会社は、社員の質が違うと言われます。強い会社に、強い人材が集まるのには、訳があります。どうすれば強い会社になれるのか、強い社員を採用するにはどうすればよいのかを考える必要があるのです。
人事は経営戦略そのもの
人事を軽視する会社は必ず「人が育たない」という壁に直面します。逆に、社員を資産と見なし、人事施策を経営戦略と一体化した会社は、持続的に成長します。未来を支えるのは人であり、経営者の社員に対する視点そのものが、会社の命運を分けるのです。
あなたは、自分の事業戦略を机上の空論に終わらせますか?