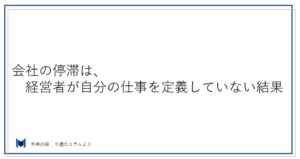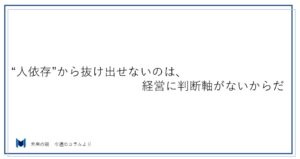第139号:人がいない会社の共通点は「経営者の時間」にある
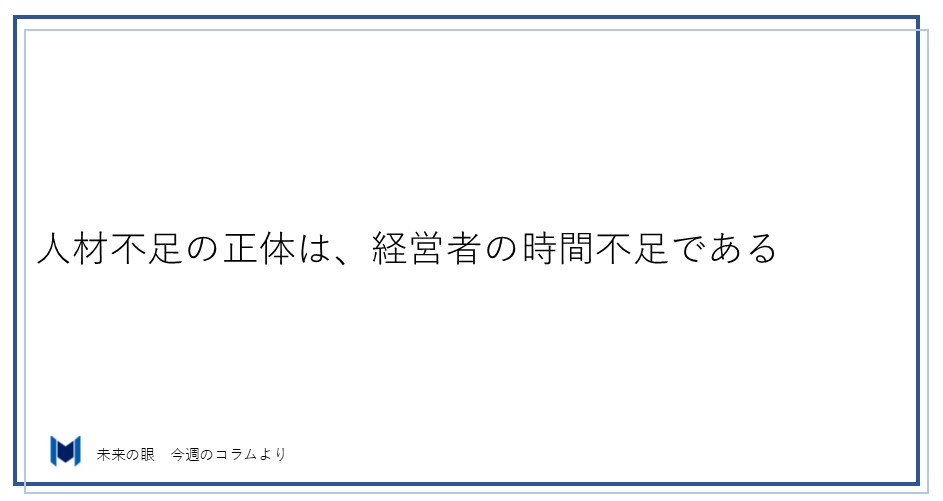
仕事はあるのに人材がいない
「仕事はあるのに、人がいない」。この言葉ほど、今の日本企業の現状を象徴するものはありません。受注は増えている。顧客からの依頼も絶えない。にもかかわらず、現場を動かす人材が足りず、結果的にチャンスを逃してしまう。経営者の多くがこの状況に頭を抱えています。
果たして本当に「人がいない」のでしょうか。少子高齢化や採用市場の競争激化といった外部要因は確かに存在します。しかし、その影にもっと深い構造的な原因が潜んでいます。それは、「経営者の時間が、未来をつくる仕事に使われていない」という事実です。
現場に時間を奪われる経営者たち
多くの経営者は、日々の業務に追われながら、「自分が動いた方が早い」、「社員に任せると余計に時間がかかる」、「最終的な責任は自分にあるのだから」と感じています。
その結果、経営者自身が営業の最前線に立ち、顧客対応に追われ、現場の細部にまで関与してしまう。確かに短期的には成果が出るかもしれません。しかしその一方で、社員は自ら考える機会を失い、幹部は意思決定の経験を積むことができず、組織は「社長がいなければ回らない」状態に固定されていきます。
この状態が続けば、経営者が現場にいる限り、組織は“経営”ではなく“管理”の延長線上に留まり続けます。仕事は増えるのに、動かせる人が育たない。人材不足の根本原因はここにあるのです。
人材不足の本質は、「経営者の時間の使い方」にある
人手不足に悩む経営者の多くは、採用活動に力を入れ、求人広告に投資し、人材紹介会社と契約します。しかし、どれほど募集をかけても、「人が足りない」という問題は解消されません。
なぜなら、経営の時間配分そのものが“短期の成果”に偏っているからです。経営者が現場に張り付き、数字を追うことに多くの時間を費やすと、組織全体の時間も“今日を回す”ことに費やされます。
ある企業では、経営者が毎日午前中を現場確認と営業報告に費やしていました。その結果、経営会議は後回しになり、幹部たちは「社長の指示を待つ文化」に染まりました。そこで思い切って、社長が“未来戦略の日”を策定する確保したのです。最初は何も進まなかったものの、数ヶ月後には会議のテーマが「今日の売上」から「3年後の組織構想」に変わり、半年後には幹部が自ら提案を持ってくるようになりました。
経営者の時間を変えることが、組織の思考を変える起点になるのです。
「手放す勇気」が未来を生む
経営者の仕事は、“自ら動くこと”ではなく、“動ける人をつくること”です。しかし現実には、「任せたが失敗されたくない」「顧客を失うのが怖い」といった心理が、経営者の手を現場に縛りつけています。経営者がすべてを抱え込む限り、社員は成長しません。社員が自分で考え、責任を持って行動するには、経営者が“任せる覚悟”を持つことが不可欠です。
実際、ある経営者は長年、自分が担当していた大口顧客を幹部に任せました。初めのうちはトラブルが続き、社長は何度も介入したくなったと言います。しかし、あえて我慢して見守った結果、半年後には幹部がその顧客から信頼を勝ち取り、新規案件まで獲得するようになりました。
「手放す」とは、単に業務を渡すことではなく、社員の可能性を信じることです。
経営者の仕事とは、“時間を未来に投資すること”
経営者の最大の資源はお金でも人材でもありません。それは“時間”です。
経営者がどこに時間を投資するかで、会社の未来は決まります。
短期の数字ばかりを追う経営は、社員を疲弊させます。
逆に、経営者が未来の戦略や人材育成に時間を投じる経営は、社員を成長させます。
例えば、採用の面接にすべての時間を使うのではなく、「3年後にどんな組織をつくりたいか」を考える時間を持つ。会議で細部を詰める代わりに、「幹部にどんな意思決定を任せるか」を設計する。その積み重ねこそが、組織を“社長依存”から“自律組織”へと変えていく唯一の方法です。
経営者が未来を語る時間が増えるほど、社員は自分の役割を理解し、主体的に動き始めます。社員が会社を信じるのは、経営者の言葉ではなく、“時間の使い方”に現れる本気です。
社員に任せる勇気と、失敗を許す覚悟を持っていますか?