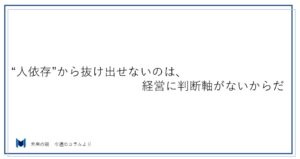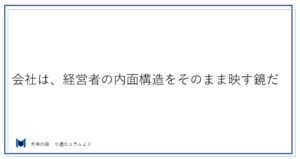第141号:社長しか経営を語れない会社が止まる理由
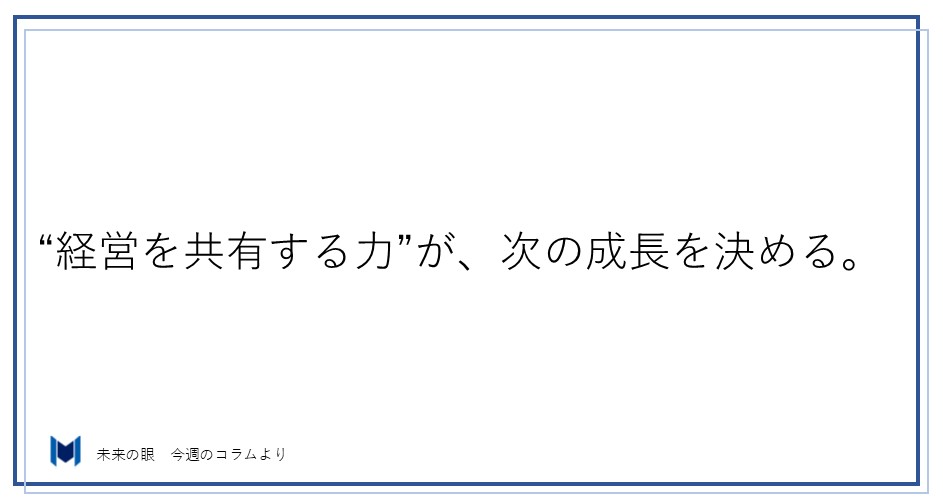
経営を語れるのは自分だけ
数字の話や業務の相談はできても、「会社をどう成長させるか」「次の一手をどう打つか」を語れる相手がいない。そんな静かな孤独を感じる経営者は少なくありません。
社長がいなくても会社が回る。それが理想だと分かっていても、実際には社長が止まれば会社が止まる。会議では誰も戦略を語らず、社員は「指示が出るのを待つ」。そして社長だけが未来を考えている。この構造が、組織の成長を止める最大のボトルネックです。
社長以外に“経営を語れる人”がいない会社の現実
多くの経営者は、ある時期から「自分がいないと何も決まらない」ことに気づきます。報告会議では、社員が数字を読み上げ、社長がその場で指示を出す。社員は“経営判断を支える参謀”ではなく、“報告する部下”のまま。気づけば、全員が“社長の頭の中を読むゲーム”に疲弊しています。
現場は日々忙しい。だからこそ、「なぜ今この方針なのか」「この投資の意図は何か」を話す時間が失われ、やがて社長の構想は共有されず、社員にとっての“経営”は「自分とは関係ないもの」になってしまいます。この状態が続くと、組織は「思考する組織」から「指示待ちの組織」に変わります。
経営を語れる幹部がいる会社の強さ
経営を語れる幹部が社内にいる会社は、明らかに空気が違います。社長がいなくても現場が自律的に動き、意思決定が速い。幹部たちは単なる「社長の右腕」ではなく、「共に未来を構想する仲間」です。会議では本音の議論が交わされ、課題が見えれば即座に改善案が出る。そこには“社長の指示を待つ”という姿勢はなく、「自分たちが会社をつくっている」という当事者意識が根づいています。そうした組織では、社員一人ひとりの発言に熱があり、挑戦に迷いがありません。
一方で、社長しか経営を語れない会社では、どうしても社長が“描く人”、社員が“動く人”という構図が固定化されます。社長が未来を語れば語るほど、そのビジョンを理解しきれない現場との温度差が生まれ、会社のスピードが落ちていくのです。やがて、社長自身が意思決定のボトルネックとなり、どんなに優秀な人材を採用しても、組織が広がるほどに負荷だけが増していきます。
経営を語れる幹部を育てるというのは、単に「頼れるNo.2をつくる」ことではありません。社長の思考を共有し、同じ未来を構想できる仲間を増やすということです。彼らが育てば、会社はひとつの意志で動くようになり、変化に強くなります。だからこそ、幹部育成は採用や売上よりも先に取り組むべき“経営の土台づくり”なのです。
経営を“共有できる”会社が次の時代を勝ち抜く
市場変化のスピードが増す今、経営の舵取りを支えるのは、社長一人のカリスマ性ではなく、経営を共有できるチーム力です。構想を語り、判断を共有し、意思決定を共に行える幹部がいれば、会社は変化にも柔軟に対応できます。経営とは未来を描く行為であり、経営を語れる人が増えるということは、未来を共に描ける人が増えるということです。その瞬間から、会社は“社長の会社”ではなく“自分たちの会社”へと変わります。経営を語れる人がいない会社は、人材がいないのではなく、語る場と仕組みがないだけです。まずは月に一度でもよいので、数字ではなく構想を語る時間を設けてください。その小さな場が、経営を共有する文化の始まりとなり、会社を次のステージへと導きます。
あなたの会社で「経営」を語れるのは、何人いますか?