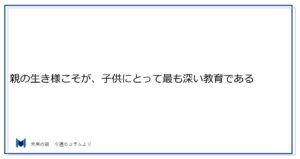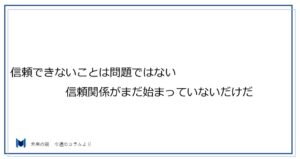第115号:経営者が考えるべき“死後の経営”と家族への伝言
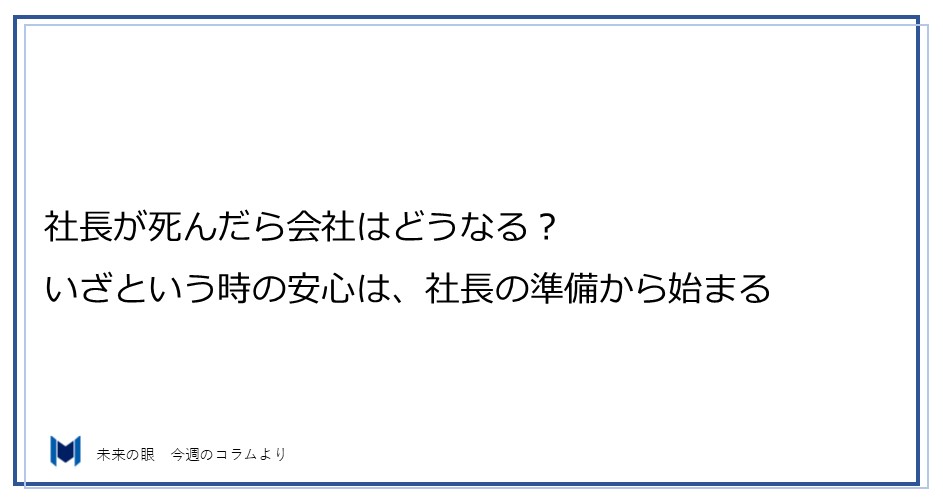
「ご自分が、亡くなることを想定していますか?」と、コンサルティング前の雑談で経営者に投げかけた質問です。似たようなことをお聞きすることもありますが、異口同音に「考えていない」とおっしゃいます。多くの経営者にとって、自分の「死後」を考えることは、どこか遠い話のように思えるのかもしれません。
経営者であるあなたが、ある日突然、事故や病で命を落としてしまった時のことを想像してみてください。何も引き継がれていない状況で、残された家族がどれほど混乱し、戸惑い、そして悲しみながらもさまざまな手続き、決断を下していかなければならないことを…。
家族の死を受け入れるだけでも辛いことであるにも関わらず、そこに、会社経営という難題と取り組まなければならないのは、想像を絶する苦行です。残された家族が「経営とは何か」を学び始める前に、目の前の処理すべき問題に疲弊しきってしまいます。
実際、ある知人の経営者が50代で急死した時、その家族は経営実態を詳しく理解していませんでした。書類の保管場所も見当がつかない、何から手を付け、どこに相談すればよいのかも分からないと途方に暮れたと話していました。悲しみに耐え抜こうとしている中での、社員から詰め寄れた時、生きた心地がしなかったと語っています。
経営者の死は、避けようがありません。しかし、その時のために準備をすることはできます。会社をどうしたいのか、誰に託したいのか、どういう選択肢が望ましいと考えているのか、それを明文化する。そして、自社が大事にしている考え方、今後の事業のあり方、主要な取引先、幹部社員の力量、借入残高や保証人関係、株式の構成、顧問税理士や弁護士の連絡先などを、家族がわかるように整理しておくことです。
つまり、「会社の取扱説明書」となるようなものを作成することです。そして、それをもとに家族と対話する時間を持つことをお勧めします。「うちの家族は会社に興味がない」「事業の話なんかしても理解されない」と経営者は言いますが、経営の世界は複雑で難しいもので、家族が理解しにくいのは当然です。
ですから、「なぜこの会社を守ってきたのか」、「仕事のやりがい」、「仕事の面白さ」を伝えながら、家庭内に仕事の理解者を増やし、まるで「もう自分の会社である」かのように大切にしたい、つまり、感情移入できるようにしていく工夫は必要です。実際に経営を引き継ぐか否かは、託された側が決めることですが、その判断材料となる経営者自身の意思を伝えておく価値はあると思います。
経営者が自分の死を考えることは、「自分がいるからこそ成り立っている会社」から「自分がいなくても回る会社」へと進化させることでもあります。会社が一人のリーダーに依存している状態では、経営者の病気や事故、あるいは急な引退に直面した時に、組織はすぐに機能不全に陥ります。
業績が悪化するだけでなく、社員の離職、顧客との信頼関係の崩壊、取引先との契約破棄、金融機関からの信用低下など、連鎖的に問題が発生してしまう可能性があります。また、「自分がいなくても事業が継続できる状態」を作っておくことが、社内外からの信頼も厚くなり、幹部も育ちやすくなります。
経営者という立場において、「終わり」を想定することはまるで「弱さ」や「後ろ向き」のように捉えてしまいがちです。自分の死に触れることは縁起でもない、自分はまだまだ死ねない、というように避けたい内容であることは確かです。
しかし、人間はいつか死にます。だから、ここまで書いてきたように準備する。少し強烈な表現をしますが、経営者は「死ぬことを前提に経営する」ことです。これこそが、永続企業を作るための最強の思考法です。
愛する家族と社員のために、今日からその準備を始めませんか?