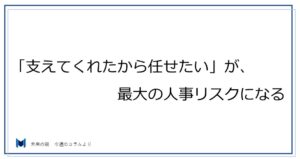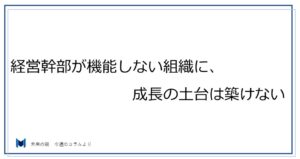第125号:人事を任せるな。
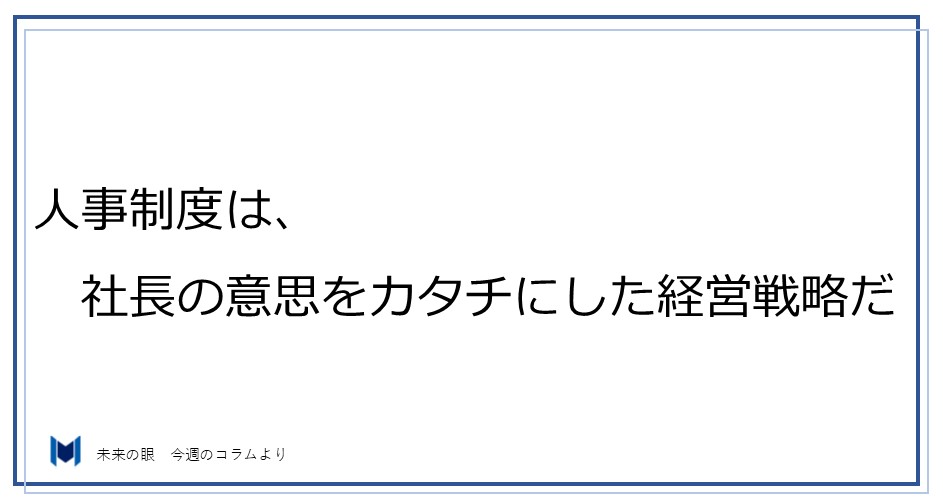
「社員が増えてきて、できる社員とできない社員の差がはっきりし始めています。ところが、その差をマネジャーが理解できていません。人事に評価できる仕組みを考えるように指示しましたが、全く進んでいなくて困っています。」というご相談を頂きました。
「人」のことは、人事に任せているという経営者は少なくありません。事業成長に人材が追い付かない、業績の停滞、幹部が育たない、社員が定着しないといった問題の背景には、経営者自身が「人を見る」ことを放棄していることが少なくないのです。
「人事に任せている」という場合、多くは労務管理や賃金管理の延長線上で評価制度が設計できると考えているようです。ここに、経営者の人事評価に対する誤認があるのではないかと考えています。
人事評価制度の構築について留意しなければならないことの1つに、「職務遂行能力」があります。「与えられた職務や役割に対して、業務を滞りなく進めることができる」ということですが、大多数の人事担当者は、全社員の「業務」を知りません。
経営者は、この根本的な問題を脇に置いたまま「評価制度」構築を命じてしまいます。人事とは、「人を通して事業を成功に導く経営手段」です。逆に言えば、「人を見誤る」ことは、「経営を誤る」ことに直結します。ですから、絶対的に譲ってはいけない部分は、経営者ご自身が考えることが重要だと考えています。
こうした内容をお伝えすると、ご自身の生い立ち、会社設立の想いを熱弁してくださる方がいます。それはそれとしてとても大切な要素ではありますが、実務的には、「誰に、どのような役割を与え、どのような未来を託すか」というようなことは、経営者しか描けないテーマなのではないでしょうか。
ぼんやりと描いている方も、もちろんいらっしゃると思います。それを明確化していくことで、事業と人材がしっかりと結びついていきます。特に、「幹部人材の見極め」でその効力を発揮します。多くの経営者が、忠誠心や功労によって昇進を決めてしまい、結果として「戦略に合わない幹部」が上に立ち、組織が硬直するという問題が起きています。
幹部候補を見る際には、「この人は、次の事業フェーズを担えるか?」という視点が不可欠です。「事業を拡大したい」、「収益性を高めたい」、「組織を若返らせたい」などの、事業の方向性や課題に対応できるだけの資質・思考・関心を持つ人材を選抜する必要があります。
経営と人事が分離していては、いつまで経っても「人」が経営の武器になりません。戦略に合った人材の登用こそが、企業の命運を左右するのです。
さて、経営者が「人事の肝」を考えるもう1つのメリットがあります。人事評価制度とは、「会社から社員に対するメッセージ」だということです。つまり、会社が、「何を大事にしているか」「何に価値を置いているのか」を昇進や昇格、評価結果を通じて現場に伝えることができることです。
どれほど優れた人事評価制度を構築しても、「経営者が発する一言」、「昇進していく社員たち」が制度の趣旨とかけ離れていれば、社員は絵に描いた餅のような制度やそれを放置する会社に冷ややかになっていきます。
人材の確保が困難になり、離職率が高止まりしている今、多くの企業が「採用が難しい」「人が辞める」「幹部が育たない」といった課題に直面しています。これらはすべて「人事の問題」であると同時に、「経営の問題」でもあります。
結局のところ、経営者が人事制度に責任を持つことは、「自らの哲学」と「事業ビジョン」を基にした企業の未来をつくる「人事」の出発点となるのです。
あなたの会社の人事制度は、誰の価値観でつくられていますか?