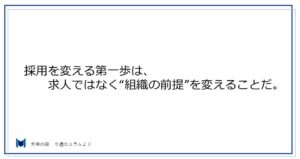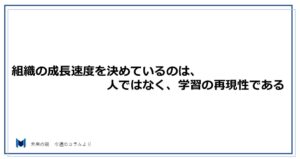第146号:複雑性を扱えない会社の限界点
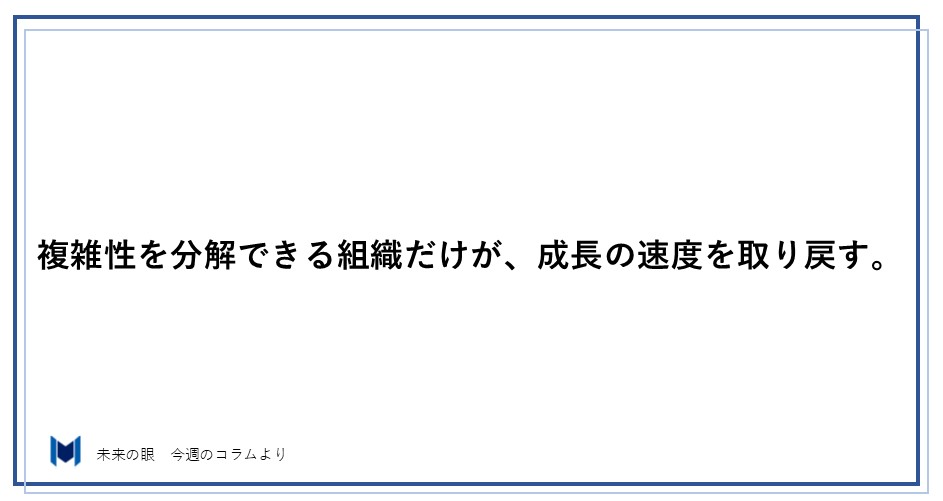
経営者が感じている八方塞がりの正体
「もっと成長できるはずなのに、どこかで止まってしまう」という感覚を抱えてしまうことは、決して珍しいことはではありません。現場は忙しく、管理職は疲弊し、経営会議では「やるべきこと」は山のようにあるのに、「やるべきことが多すぎて、何から手をつけるべきか分からない」という停滞感が会社に漂っている。
この停滞は、人材の質でも、制度の整備不足でもなく、もっと深いところにあります。それは、組織の複雑性が増大しているにも関わらず、それを分解し、構造化し、対処可能なレベルに設計し直すこと避けてしまうことが原因です。
現場・管理職・経営のいずれの階層でも、複雑性に押しつぶされ、判断が鈍り、結果として事業成長のスピードが低下してしまいます。この構造を理解しなければ、人材施策も組織改革も成果を上げることは難しくなります。
単発施策が効かなくなる理由
顧客ニーズの多様化、人手不足による同一メンバーへの負荷集中、多重タスク化、管理コストの増大、属人化したノウハウのブラックボックス化などといったように、これらが相互に影響し合い、全体として複雑系の様相を呈しています。
ところが、多くの企業ではこのややこしい状況への深入りを避けることがあります。複雑性を“量の多さ”として認識し、絡まりあった因果関係を見逃してしまうことがあります。「仕事が多すぎる」「指示が細かすぎる」「管理項目が増えすぎている」と現象面ばかりに囚われて、相互依存性の問題を置き去りにしています。
あるいは、解決策をまるでもぐらたたきのような施策で済ませようとしてしまうことがあります。複雑性の問題は構造そのものが歪んでいるため、単発施策では上手くいく方がまれです。そのため、経営者自身が、自分の頑張りで処理しようとすることがあります。
全体の複雑性が増えたとき、経営者は自分が決めれば早いと判断しがちです。しかし、複雑性は中央集権では処理しきれないため、結果として、意思決定が遅れ、現場は判断を待ち、幹部の成長は止まり、組織の動きは鈍化します。
成長を阻むのは“人材不足”ではなく、複雑性の分解力の欠如
「人が増えれば」「優秀な社員がいれば」…と考えてしまいますが、人の問題ではなく、ここにある厄介さを分解し、対応できる能力が不足しているのではないでしょうか。それは、「何が根本要因で、何が派生しているのか」「何を優先し、何を切り捨てるのか」「個別の現象ではなく、パターンを見極める」です。
現場では「忙しいから説明できない」、幹部は「感覚でやってきた」、経営者は「自分で決めたほうが早い」と、無意識の習慣が出来上がっています。そこには、複雑性を分解する隙がありません。
複雑性を地図化し、圧縮し、委譲する
当たり前の話ですが、今の経営環境は入り組んでおり、難易度が高いです。そのため、分解力を組織全体で高める必要があります。
複雑性の“可視化は必須です。複雑性は目に見えないため、プロセス・判断ポイント・承認経路・例外処理・暗黙知を棚卸しし、“何が複雑性を生んでいるのか”を見える化することが重要です。経営会議で扱うべきは「問題」ではなく、「複雑性の地図」です。
次に、複雑性の圧縮です。「捨てる・まとめる・任せる・標準化する」で、経営者が明確にルール化を図ることが求められます。
そして、分解した複雑性を委譲可能な単位に変換します。幹部育成の本質は、スキルの伝達ではなく、複雑性の一部を委譲できる状態をつくることです。幹部に丸投げするのではなく、「この複雑性のこの領域を任せる」という明確な線引きが必要です。
最終的には、こうした築き上げる組織OSの更新を行うことです。複雑性の分解力は、一部の優秀な管理職ではなく、組織のOSが支えるべき能力です。
あなたの組織では、複雑性は「どこで増幅」し、「誰が」その負荷を背負っていますか?