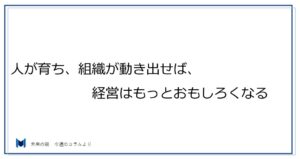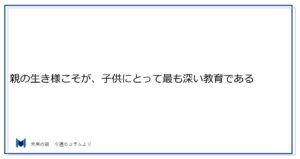第113号:人手不足時代の人材戦略 ~確保・定着・活用を実現する企業の在り方とは~
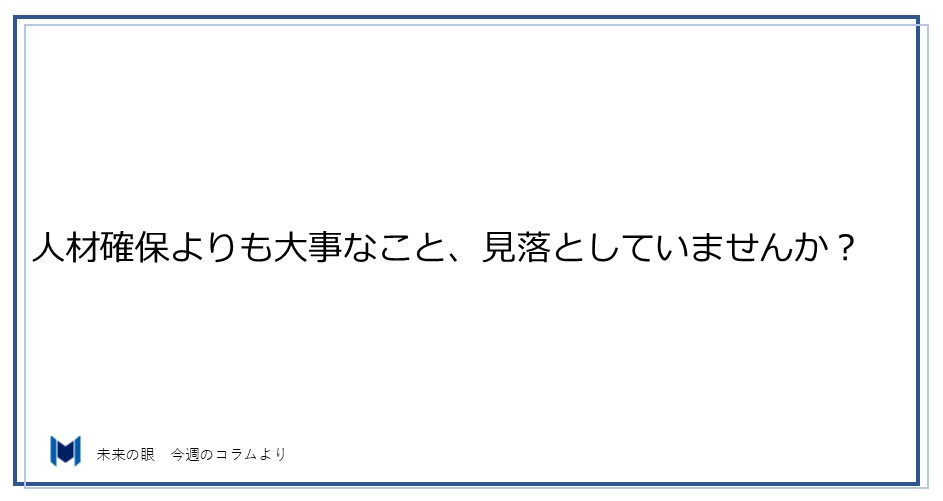
今年も新年度を迎え、全国各地で入社式が行われました。真新しいスーツに身を包んだ新入社員たちは、希望と緊張を胸に、社会人としての第一歩を踏み出しました。この会社で成長したい、誰かの役に立ちたい、そんな期待を持って入社式に臨んだのではないでしょうか。
この季節は、単に新入社員を迎え入れるだけではなく、組織全体で「人材をどう育て、どう活かすか」を考える貴重なタイミングでもあります。いかにして彼ら・彼女らがこの会社で成長し、活躍し、長く働き続けてくれるか――という視点での人材戦略が求められています。
あえて言うまでもありませんが、これから日本の人口は確実に減少し続けていきます。人手不足の原因として、労働人口の減少は避けられない事実です。とくに働き手となる生産年齢人口(15〜64歳)は、今後ますます減っていくことが確実です。この変化は、業種や地域を問わず、あらゆる企業に人材の確保とその活用という共通の課題を突きつけています。
採用難に留まらず、既存社員への過度な負荷、サービス品質の低下、生産性の伸び悩みなど、経営のあらゆる領域に波及しています。とくに中小企業や地方企業では、人材の確保が企業の存続に直結する死活問題となっており、もはや待ったなしです。
人手不足の原因である労働人口の減少が進む中で、企業が講じるべき人材確保の方法も根本的な転換が求められています。企業側が「人を採りたい」と考えていても、求職者が少ないために人材の獲得競争が激しくなります。求職者にとって選択肢が多く、有利な条件で職を選べるようになります。
つまり、これまでのように、求人広告や紹介会社を頼り、母集団を増やすだけでは不十分です。「企業が選ぶ時代」から「企業が選ばれる時代」へと移行しています。経営者がまず取り組むべきは、自社の魅力や存在意義を明確に発信することです。ビジョン、ミッション、社風、働き方、社員のリアルな声まで含めて、求職者が「ここで働きたい」と思える情報を整えることが不可欠です。
また、柔軟かつ多様な人材活用も競争力の源泉になります。高齢者、主婦、外国人、障がい者、副業・兼業の専門人材など、これまで十分に活かしきれていなかった層を戦力として取り込む柔軟さが、これからの組織には求められています。
とはいえ、人材を「採る」だけでは課題は解決しません。今後ますます重要となるのが、いかに優秀な人材を「辞めさせず、定着させて、活かし続けるか」という視点です。以前のコラム「第111号:離職率を利益に変える 組織づくりの本質」でも書いていますが、社員の離職理由は「職場の人間関係」「労働条件」「給与」となっています。
離職の原因は人によって異なりますが、「人間関係の悩み」「労働条件への不満」「給与の水準」に関する問題とどのように向き合うかによって、離職を防ぐ施策へと昇華させることができます。日々のコミュニケーションや制度設計に「一人ひとりの声を聞く姿勢」があるか、働く人の未来を「見える化」しているか、そして自分らしい働き方を「選べる」環境があるか――この3つの視点が整っていれば、社員は簡単には離れていかないのではないでしょうか。
これらに対処することは、社員一人ひとりと向き合い、「人材としての資産価値を高める」ことにつながります。一見面倒なようにも思いますが、一人ひとりの社員をよく知ることは、「人」を最大限に活かすためには必要不可欠です。
年齢やスキルだけでなく、価値観、得意・不得意、働く理由、人生の目標などといった「個の理解」によって、力の引き出し方は変わってきます。「適材適所」は社員を知る姿勢があってこそ可能となります。それは、社員にとっては、「自分を理解してくれた」と感じることにもなり、組織への信頼や貢献意欲は飛躍的に高まります。
さらに、“個を知る”ことはマネジメントの無駄を減らし、業務効率の向上につながります。的確な指示、無理のない役割設計、適切なフォローが揃うことで、業務上のミスや摩擦、やり直しの頻度が減り、結果的に組織全体の生産性は上がります。
労働力の確保が難しい今だからこそ、人材に投資し、その可能性を最大限に引き出せる企業が、今後の成長を牽引していくでしょう。今いる社員が「この会社で働き続けたい」と思えるような環境づくりこそ、採用よりも難しく、しかし企業価値を最も高める投資なのです。
あなたの会社で、働く魅力は何ですか?