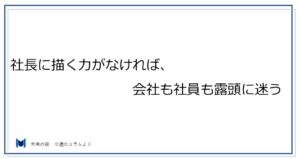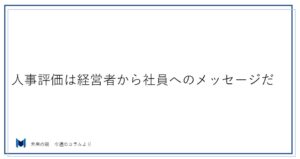第130号:誰でも語れる人事の話が負債を生む理由
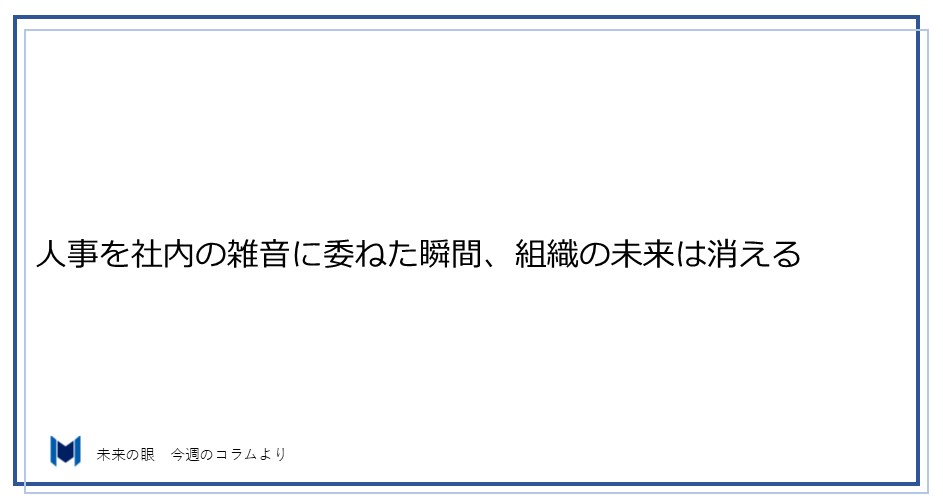
経営者を悩ませる「人事の迷走」
中小企業の経営者から、このような声をよく聞きます。「人事の話になると、社員も幹部も、みんな好き勝手に意見を言うんです。採用はもっと増やすべきだ、評価は不公平だ、給与を上げろ、どれももっともらしく聞こえるのですが、結局、何が正しいのかわからなくなるんです。」
こうした社員の意見を聞き、対策を打ったが失敗したという経営者の話は決して珍しい話ではありません。なぜ人事の話はここまで好き勝手に語られ、会社を迷走させるのでしょうか。
人事は「全員が当事者」だから意見が乱立する
営業戦略や製造の改善などといった専門性が高い分野に関しては、意見を控える社員が大半です。ところが、人事の話になると、誰もが専門家のように、社員も幹部も一斉に口を開きます。その理由は明確で、人事は全員社員にとって当事者意識を持って語れるテーマだからです。
評価される社員は、「なぜ自分は昇進しないのか」と考えます。
給与や賞与に関わる話題は、誰にとっても切実です。
異動や配置の噂は、直接自分の将来に結びつきます。
しかも、人事の判断は数値だけでは測れず、必ず人の感情に触れます。
「どうしてあの人が昇進するのか」
「なぜあの部署ばかり人が増えるのか」
こうした感情が意見となり、社内で連鎖的に膨らんでいくのです。
つまり、人事は素人でも口を出せるテーマであると同時に、感情の影響を強く受ける領域であり、だからこそ好き勝手な意見が乱立するのです。
好き勝手な意見に従うと、人事は迷走する
経営者にとって厄介なのは、こうした意見が社内の空気を変えてしまうことです。声の大きな社員や幹部の意見に押され、人事が場当たり的に動くと、次のような迷走が始まります。
1.評価制度の迷走
不満に応じて制度を頻繁に変更すると、基準はあいまいになり、「結局は社長の感覚次第」という不信感だけが残ります。
2.採用方針の迷走
「若手を採れ」「即戦力が必要だ」と意見に従って採用を繰り返すと、組織構成は歪み、定着率が下がります。
3.教育・研修の迷走
その場しのぎの研修は効果が薄く、「また形だけの施策か」と社員が冷める原因となります。これらの迷走は、表面的には「改善しているように見える」ため厄介です。
しかし根本原因は何ひとつ解決されず、優秀な人材から順に辞めていく悪循環に陥ります。
人事は経営の専門領域──社長や人事部の丸抱えでは限界がある
前回のコラム「第129号:人事は「制度」ではなく「未来の設計図」がなければ機能しない」にも書いていますが、本来、人事は人と組織を活かして経営の未来を作り上げる専門領域です。
数年先の将来、何十年先の未来、会社がどのような事業構造になり、どのような存在であり続けるのか。その未来像を描かなければ、採用も評価も育成も一貫性を持たせることができません。
しかし、現実には次のようなケースが少なくありません。
・評価制度は外部コンサルタントに丸投げ
・給与設計は社労士に依頼
・採用は人材紹介会社任せ
・育成は研修会社にスポットで発注
一見すると効率的に見えますが、結果としてバラバラな人事施策の寄せ集めになりがちです。評価と給与が連動しない、育成と昇進がつながらない、採用で求めた人物像と現場の実情も噛み合わないという事態に陥っていることがあります。その歪みが社員の不信感となり、定着率や生産性の低下を招きます。
だからこそ、経営者自身が全体の設計思想を握ることが欠かせません。未来の組織像を明確に描き、その実現に必要な評価・給与・育成・採用を一貫した方針で設計する。全体像を経営者が主導することで、バラバラの施策は一貫性を持たせることで、組織は初めて安定して力を発揮します。
経営者が踏み出すべき次の一歩
もし、社内で人事に関する不平・不満の声が上がっているなら、それは組織が次の段階に進むべきサインかもしれません。
まずは、経営者自身が未来の組織像を描き、どのような人材を育て、どのような仕組みで活かしていくのかを静かに見つめ直すことから始めてください。
あなたの会社には、組織の未来を生む“一貫した物語”がありますか?