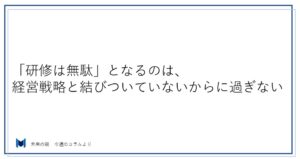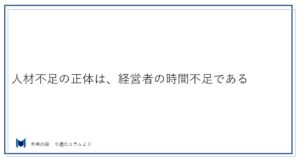第138号:経営者が見直すべき“自分の役割”
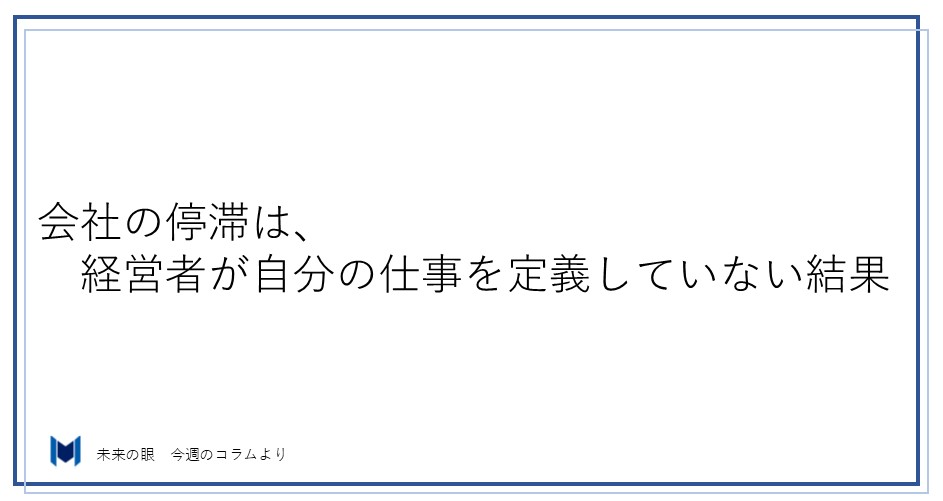
社員が動かない本当の理由
「どうして社員は言った通りに動かないのか」「幹部が育たないのはなぜか」と、悩みを抱えている経営者は多いのではないでしょうか。社員の意見を聞き、研修に送り出し、評価制度も刷新したのに成果がでない。そうした経営者の努力が報われない、日々を繰り返すのはもう終わりにしませんか。
この問題から解放されるためには、経営者の仕事の定義を明確にすることです。
プレーヤー経営者の罠
ある製造業の社長は、創業期から自ら営業に走り、顧客を獲得し、現場のトラブルにも直接対応してきました。その姿勢は社員の信頼を集め、会社を伸ばす原動力になってきました。ところがある時から、「自分が現場に出過ぎるために、幹部が決断していない」「幹部が社員を育てられない」といったことが、気になるようになっていきました。
社長は「人材が育っていない」と焦りを感じていましたが、実際には社長が幹部の仕事をしていたのです。
人材制度が空回りする理由
評価制度や給与制度を導入しても、社員に響かない会社があります。その背景を探ると、たいていは「経営者の役割」が定義されていない。つまり、どの方向に進むためにどんな人材を求めるのかが示されていないのです。
「とりあえず大手がやっている仕組みを真似する」「人事コンサルに言われた通りに制度を入れる」というように、「自社に人事制度」を入れる目的と基準が曖昧になっていることが多々あります。
結果的に、社員は「評価される・されない理由が分からない」「何をすれば高評価されるのか」がはっきりしないために、制度疲労が起こります。
社会環境が突きつける現実
かつての日本では、経営者が細部に入り込み、社員が「ついていけば安泰」という構造が機能しました。しかし今は違います。少子高齢化による人材不足、キャリア観の多様化、終身雇用の崩壊。こうした社会環境の中で経営者が「社員をどう使うか」だけを考えていても、優秀人材は定着しません。
社員は「この会社でどんな未来が描けるのか」を敏感に見ています。未来像を描き、自らの仕事をそこにどう位置づけるかを示せない経営者には、人も組織もついてこないのです。
経営者が立ち止まって考えるべき問い
経営者として、あなたは日々の業務に追われる中で、今もなお「優秀なプレーヤー」としての自分を維持することに満足していないでしょうか。本来、経営者の価値は「自分が動いて成果を出す」ことではなく、「組織全体を成果に導く仕組みを描く」ことにあります。
幹部が意思決定できないのは、本当に彼らに力がないからでしょうか。それとも、権限と責任を経営者が手放していないために、試行錯誤する機会を奪ってしまっているからではないでしょうか。
人事制度や評価の仕組みが形骸化するのは、運用の問題だけではなく、すべてが場当たり的に運用されているからではないでしょうか。
経営者自身が「旗を振る姿」を曖昧にし、「とりあえず、社長についていけば食いぱっぐれないから…」と社員の意欲や主体性を発揮させる機会を奪っていないでしょうか。
経営者の仕事を再定義する
経営者にとって「外すべき業務」を決めるのは、単に時間の確保の問題ではありません。それは、自分の存在意義を「現場のエース社員」からの脱却し、「未来を創造する立場」になると決めることです。
営業数値の細かい管理や、日々の売上チェック、顧客のクレーム対応は、幹部や現場が担うべき領域です。経営者が本当に集中すべきは、“未来を形づくる領域”です。
経営者の役割とは、細部を管理することではありません。事業展開とそれに伴う組織の在り方、人の動かし方を決めることです。「目先の延命」ではなく、いかに「未来を創造」していくかを追い求めていくことが必要なのです。
あなたは経営者ですか、それとも業務責任者ですか?