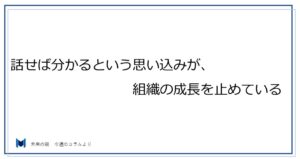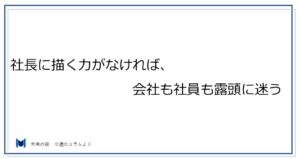第128号:社員は経費であり、将来の収益源にもなる
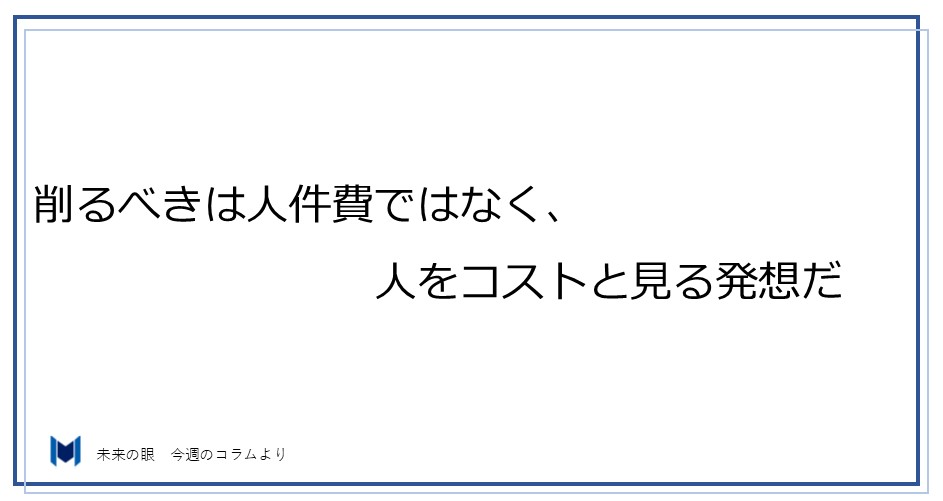
「なんで、この人たちの給与上げないといけないんだろう…と思ってしまうことがあります。」と、社員の給与を上げることに躊躇している経営者が話しはじめました。「言われたこともできない、言い訳ばっかり、都合が悪くなると辞めると言い始めるし、本当にこういう社員たちの給与を上げることが嫌なんです!」と語気を強めました。
万が一、社員が辞めたら自分が現場に出ればいいと考え、採用活動を継続しながら社員の給料を据え置きながら様子を見ていました。しかし、しばらくすると職場で中心的な役割を果たしていた社員が退職してしまいました。社長は振り返ります。「社員のことをコストだと思っている自分がいるんです。安くてよく働く、都合いい人材なんていないですよね。」
この話は決して特別な事例ではありません。経営者が「人材=コスト」という視点に縛られたとき、同じことが繰り返されるのです。
■ なぜ中小企業の社長は「人材=コスト」と考えてしまうのか
第一に、人材投資は効果が「見えにくい」ことが原因です。設備投資や広告宣伝なら、短期で数字に反映されますが、人材育成の成果は半年後、1年後にじわじわ現れ、しかも数字化しにくいものです。すぐに成果を求める経営者ほど、人への投資を「無駄」「非効率」と考えてしまいがちです。
第二に、指示命令型の成功体験が足かせになっていることもあります。社員を「従わせる」ことで成果を出してきたため、そのスタイルから抜け出すことができなくなります。結果、社員を「管理対象」「コスト対象」としか見られなくなっています。
第三に、資金繰りに追われる現実です。特に中小企業は日々の売上やキャッシュフローに敏感で、将来への投資より、目先のコスト削減に意識が向きます。こうして、人件費は「まず削るべきもの」と見なされてしまうのです。
■ 人材は「コスト」ではなく「未来を創る投資」である
人は伸びます。組織も変われます。目の前の社員を「これが限界」と決めつけるのではなく、期待し、任せ、育てれば、想像以上の成長を見せます。それを実感した経営者だけが、人を「投資対象」と見ることができます。
人材投資は単なる人事施策ではなく、経営戦略そのものです。人材への投資とは、個々のスキル向上や知識習得にとどまらず、組織力を底上げし、企業の成長エンジンを強化することに他なりません。たとえば、社員が新しい知識やスキルを身につければ、これまで受注できなかった案件に対応できるようになり、顧客からの信頼も高まります。それが業績向上につながり、企業の競争力を高めていくのです。
さらに、人材投資には「人が人を育てる」連鎖反応も期待できます。育った社員が次の社員を育て、組織全体に成長の文化が根付いていきます。これは一過性の成果ではなく、持続的な企業価値の源泉となります。
重要なのは、単に研修や教育にお金をかけることではありません。その成果をどう事業に結びつけ、どのように投資対効果を得るかを戦略的に設計し、組織に仕組みとして定着化させていくことです。この視点があれば、人は「費用」ではなく、「価値を生む資産」になります。
そして何より重要なのは、経営者自身が変わることです。人材を活かし、未来を創るのは、経営者の「人を見る目」「未来を見る力」「育てる覚悟」です。自らの視点と行動を変えなければ、どんな人材投資も効果を発揮しません。人材投資とは、実は「経営者自身への投資」でもあるのです。
■ 人材を「投資対象」と捉えた企業が生き残る
人材は最大の経営資源です。その価値を信じ、育て、活かすことができる企業だけが、どんな環境でも成長を遂げています。一方、人材をコストとしか見ない企業は、遅かれ早かれ市場から淘汰されます。実際、離職率が高く、社員の士気が低い企業ほど、業績が低迷し、組織が衰退していく事例は枚挙にいとまがありません。
「人材投資」──この視点への転換こそが、経営の未来を左右します。人に投資する勇気を持てるかどうか。そこが、企業の命運を分ける最大の分岐点なのです。
今のあなたの経営判断は、「目先の損得」と「未来の価値」のどちらに基づいていますか?