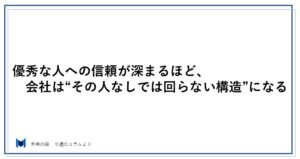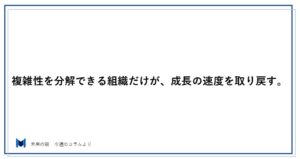第145号:採用難を突破した企業がまず壊したのは“内側の構造”だった
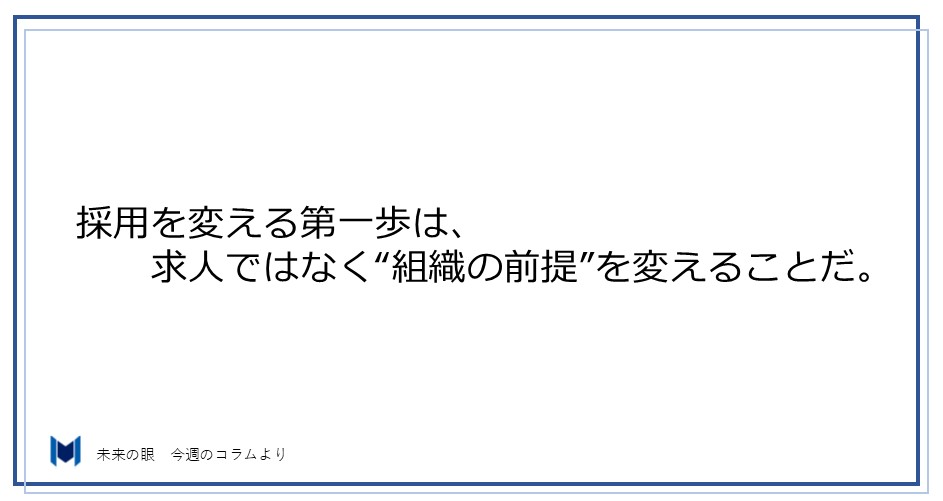
なぜ、あなたの会社だけ採用が止まるのか
「採用が上手く進まない。」求人広告に予算をかけても応募は増えず、面接に進んでも辞退が続き、内定を出してもなかなか入社に至らない。ようやく入社しても、短期間で離職してしまう。この「採用の停滞」は、市場環境の変化だけでは説明がつかない状況です。
実際、同じ採用難の市場であっても、応募者が増え、内定が決まり、1年後の定着率が上がっている企業も存在します。その差を生んでいるのは、華やかな採用広報でも、魅力的なオフィスでもありません。見過ごされがちな社内に存在する、無意識のバリアです。
外に原因を求め続けても数字が動かない、本当の理由
「人が増えないと事業が拡張できない」という事業構造で、採用活動が停滞している企業の多くは外向きの対応に偏っている傾向があります。求人媒体を変え、募集文言を改善し、SNSを強化します。しかし、成果が表れないことが珍しくありません。
「巨額の広告費を投じながらも、応募数が集まらない。」「求人票を刷新しても、面接に進む人がほとんどいない。」「応募が来ても一次面接で辞退される。」という事態に陥っている企業には、いくつかの共通点があります。
まず、「即戦力しか採用しない」という暗黙の前提が組織全体に染み付いていることがあります。もう一つは、「新人が馴染みにくい文化」が出来上がっていることです。そして3つ目は、経営者自身が「どうせ人は来ない」という諦めの感情を無意識のうちに発信していることです。
これらは誰も明確に口にしないため、経営会議でも表面化しません。しかし、採用活動に確実に影響を与えている構造的なバリアです。
応募者は何を感じ取っているのか──採用を阻む“見えない力”の正体
採用が止まっている企業の多くが見落としているのは、「採用活動は社内の空気に強い影響を受ける」という事実です。求人広告の内容がどれだけ魅力的であっても、社内に以下のような無意識バリアが存在すると、応募者は敏感に察知します。
・現場が「新人は戦力にならない」という前提を持っている
・中堅社員が「新人を教えるのは負担」と感じている
・幹部陣が「またすぐ辞めるだろう」という諦めの空気を漂わせている
・経営者が「本当に採用できるのか」と不安を抱えている
・過去の離職で組織が“守り”に入っている
・新人が溶け込みにくい“内輪の文化”が残っている
これらの空気は、面接での微妙な言い回しや、職場見学の雰囲気に表れ、応募者に無意識に働きかけてしまいます。その結果として、応募者は「なんとなく違う」と感じ、辞退や離職につながります。
これは、求人広告の問題ではなく、組織内の問題なのです。
採用が再び動き出す企業が最初に変えた“たった一つの視点”
採用の停滞を打破する企業に共通するのは、組織内にある無意識のバリアを取り払っている点です。経営者と幹部との間にある「新人は育たない」「採用しても続かない」という認識を、「新人は育つ」「入社したら辞めたくない」組織へと移行させていることです。
会社として新人を定着させることが決めてしまえば、面接時の雰囲気が大きく変ります。また、新人を受け入れる現場での対応も劇的に変化していきます。つまり、採用戦略を練るために、採用の前提を再設計したということです。
採用停滞のサインに気づけ
誰も口にはしない、採用に関するネガティブ感情。経営会議では問題として扱われることはありません。しかし、採用活動の数字には残酷なほど反映されます。だからこそ、最初に見直すべきは求人広告ではなく、社内の空気です。
採用戦略は必要です。しかし、組織内の構造を整えなければ、採れるものも取れません。あなたの会社が採用できない「本当の原因」を見ることからはじめませんか。
あなたの会社には、どんな無意識のバリアがありますか。